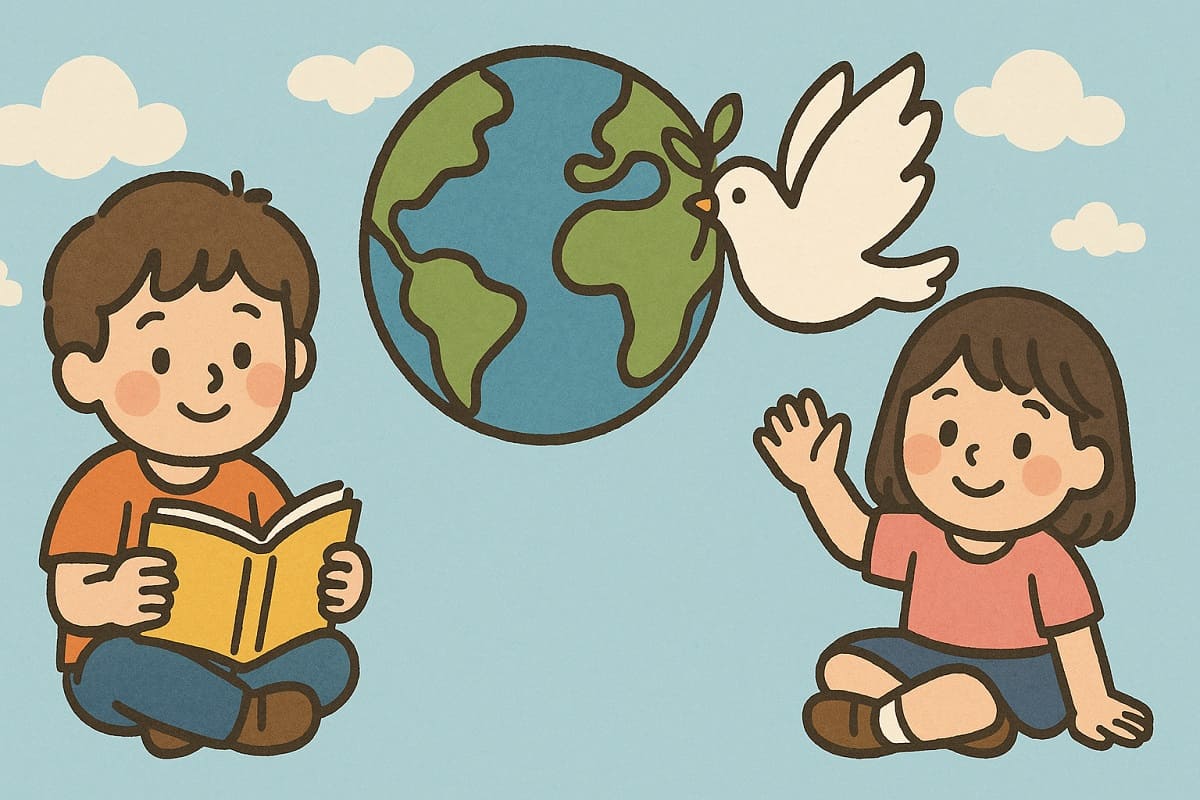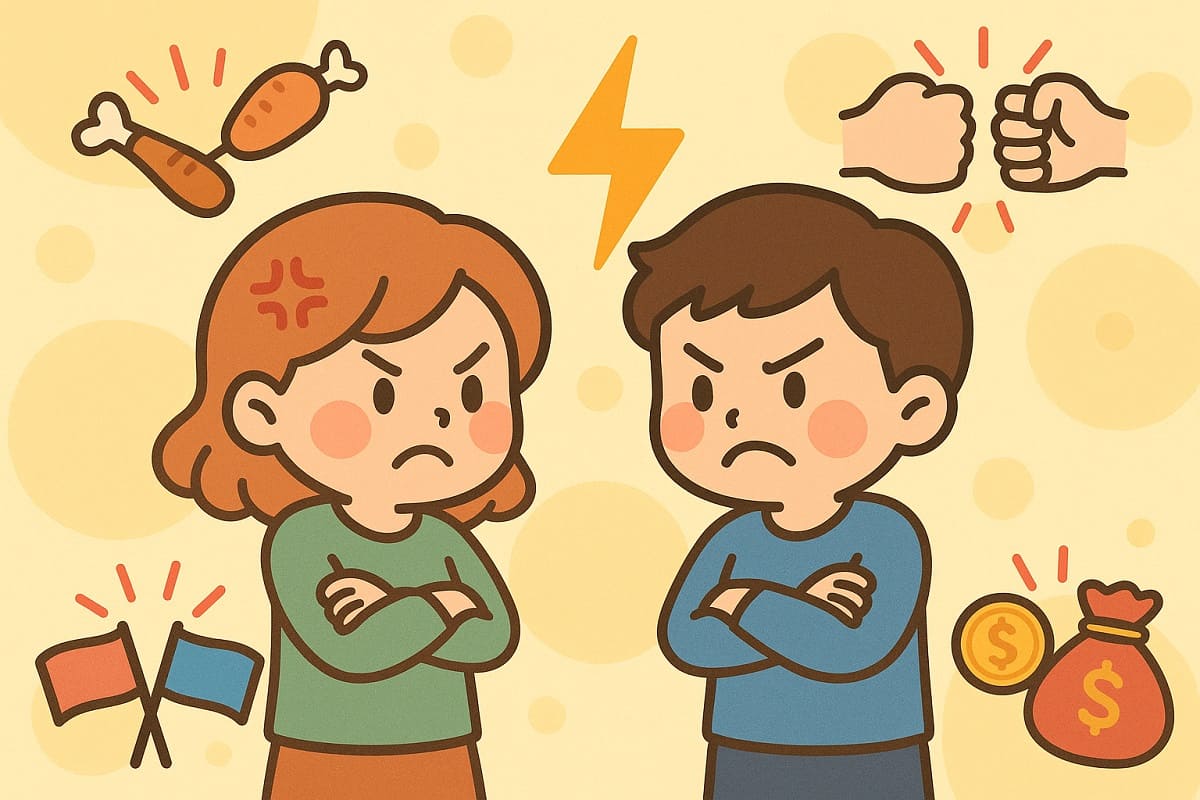AIは平和のために使える? AIで心の余裕を補おう
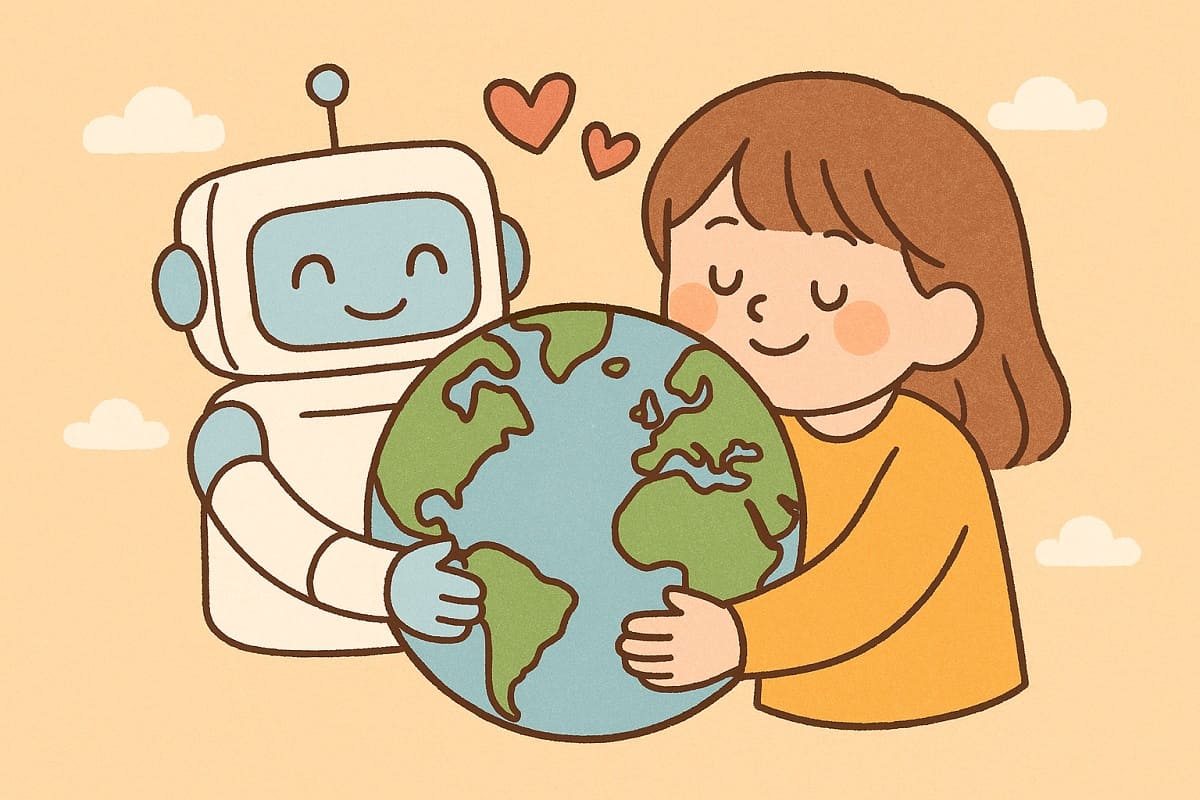
「もっと心に余裕があれば、ケンカなんてしなかったのに…」
そんなふうに思ったことはありませんか?
友達とのちょっとしたすれ違い、学校でのストレス、SNSでの言い合い…。
私たちが怒ったり、悲しくなったり、人とぶつかったりする原因には、「心のエネルギー」が足りなくなっていることが関係しているかもしれません。
この「心のエネルギー」は、心理学では「認知資源(にんちしげん)」と呼ばれます。
そして今、AI(人工知能)がその認知資源をサポートしてくれる時代がやってきました。
この記事では、認知資源とは何か、なぜそれが足りなくなると争いが起きやすくなるのか、そしてAIを使ってどうやって「心の余裕」を取り戻し、平和な社会をつくっていけるのかをわかりやすく紹介します。
認知資源ってなに? 心のエネルギーの正体
「認知資源」とは、私たちが考えたり判断したりするときに使う、脳のエネルギーのようなものです。
たとえば、難しい問題を考えると疲れたり、忙しいときにイライラしたりしたことはありませんか?
それは、頭を使いすぎてこの「認知資源」が減ってしまっている状態なのです。
人の脳は、たくさんのことを同時に考えるのが苦手です。
一度にたくさんの課題に取り組もうとすると、頭がパンクしてしまいます。
このエネルギーが足りなくなると、物事を深く考えられなくなったり、ついカッとなってしまったり、判断ミスをしてしまったりします。
つまり、心に余裕がなくなる原因の一つが、この「認知資源の減少」なんです。
認知資源が減るとどうなる?
認知資源が足りなくなると、次のような影響が出ます。
① 判断ミスが増える
イスラエルの研究では、仮釈放の判断をする裁判官の決定が、午前中のほうがはるかに多く釈放を認め、午後になるとあまり認められなくなるというデータが示されました。
つまり、人は疲れて認知のエネルギーが減ってくると、様々な情報を検討して判断することが難しくなり、深く考えずにすむ現状維持の決定を選びやすくなるのです。
② 怒りやすくなる
疲れていたり、頭がいっぱいになっていると、ちょっとしたことでイライラしてしまいませんか?
実験では、認知資源が減った人ほど、相手のちょっとした挑発に強く反応してしまうことがわかっています。
③ 思いやりが減る
人の気持ちを想像したり、共感したりするにはエネルギーが必要です。
でも、心に余裕がないと「面倒だな…」「そんなこと考えてる余裕ないよ」と感じてしまいます。
研究でも、共感することは「疲れる」と感じる人が多いことが示されています。
どうして争いが起きるの?
争いは、「意見の違い」そのものが原因ではありません。
違いに対してどう反応するかが重要なんです。
もし、認知資源が十分あって、相手の話をしっかり聞けて、冷静に判断できるなら、たとえ意見が違ってもおだやかに話し合えるでしょう。
でも、心に余裕がなかったら、相手を「敵」と感じてしまったり、「自分が正しい」と意地になってしまったりします。
研究によると、戦争を始めた国のリーダーは、平和的に解決したリーダーよりも思考が単純で白黒つけたがる傾向が強かったそうです。
これは、認知資源が足りていないときの思考の特徴と同じです。
AIが心の余裕を補ってくれる?
ここで登場するのが、AI(人工知能)です。
AIは、たくさんの情報をすばやく処理するのが得意で、人間が疲れる前に頭を助けてくれる「サポーター」のような役割を果たしてくれます。
たとえば…
① 記憶をサポートしてくれる
スマホのリマインダーやカレンダー、検索機能などは、AIが人間の「覚える」という作業を代わりにやってくれています。
その分、私たちはほかのことに頭を使えるようになります。
② 情報を整理してくれる
インターネットには情報があふれていて、どれが正しいのかわからないことも多いです。
AIは、必要な情報だけをピックアップしてまとめてくれるので、混乱せずに済みます。
③ 複雑なことをわかりやすくしてくれる
難しい問題を自分だけで考えると、頭がいっぱいになります。
でもAIに相談すれば、データを整理してアドバイスをくれることもあります。
最近では、ChatGPTなどのAIチャットボットも、勉強や仕事のサポートとして使われるようになっています。
④ 悩み相談に乗ってくれる
誰かに気持ちを聞いてほしいとき、AIに話しかけることで気持ちを整理することができます。
たとえば、イライラして相手にきついことを言いそうになったときでも、まずAIに話してみることで、感情を落ち着ける「クッション」の役割を果たしてくれます。
AIに気持ちを話してみることで、
「自分は本当は何に怒っているのかな?」
「どうやって伝えたらいいだろう?」
と、自分自身と向き合う時間が持てるようになるのです。
このように、AIはただ情報を教えてくれるだけでなく、心を落ち着けるパートナーとしても活用できるのです。
AIを平和に利用できる?
もちろん、AIが直接平和をつくってくれるわけではありません。
でも、私たちが心の余裕を取り戻し、冷静で思いやりある判断ができるようにする手助けはしてくれます。
◎ 争いが起きる前に、余裕を持てるようになる
AIが面倒な仕事を手伝ってくれれば、その分、心に余裕ができます。
その余裕が、人に優しくなれたり、ちょっとしたすれ違いに怒らずに済んだりするのです。
◎ 感情的になったときの「クッション」になれる
相手と意見が違ったときに、相手に感情をぶつける前にAIに相談することで、冷静に気持ちを整理することができます。それによって、ケンカになってしまうことを防ぐことができるでしょう。
◎ 情報の偏りをなくす
SNSでは、自分と似た意見ばかりが集まりがちです。
でもAIが多角的な意見や事実を整理してくれたら、偏見にとらわれずに相手の考えを理解しやすくなるでしょう。
まとめ:AIをうまく使って、争わない世界をつくろう
人間は、心の余裕がなくなると争いが起きやすくなります。
そして今、AIという新しい道具がその「心の余裕」を補ってくれる時代になりました。
AIは魔法の道具ではありませんが、使い方次第で私たちをもっと思いやりのある存在にしてくれる力を持っています。
これからの世界では、AIをうまく活用して、「冷静に考えられる」「相手の立場を想像できる」「ムダに怒らない」人が増えることで、
小さなすれ違いが大きな争いになる前に、おだやかに解決できるようになるかもしれません。
主な参考文献
- 岩﨑智史 (2023). 認知資源が減ると疲れるという話. Future Webマガジン. 東京未来大学.
- Danziger, S., Levav, J., & Avnaim-Pesso, L. (2011). Extraneous factors in judicial decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(17), 6889–6892.
- Cameron, C. D., Hutcherson, C. A., Ferguson, A. M., Scheffer, J. A., Hadjiandreou, E., & Inzlicht, M. (2019). Empathy is hard work: People choose to avoid empathy because of its cognitive costs. Journal of Experimental Psychology: General, 148(6), 962–976.
- Grinschgl, S., & Neubauer, A. C. (2022). Supporting cognition with modern technology: Distributed cognition today and in an AI-enhanced future. Frontiers in Artificial Intelligence, 5, 908261.
- Young, A. (2023). How to Reduce Cognitive Load With AI. Productivity Guide by Reclaim AI.