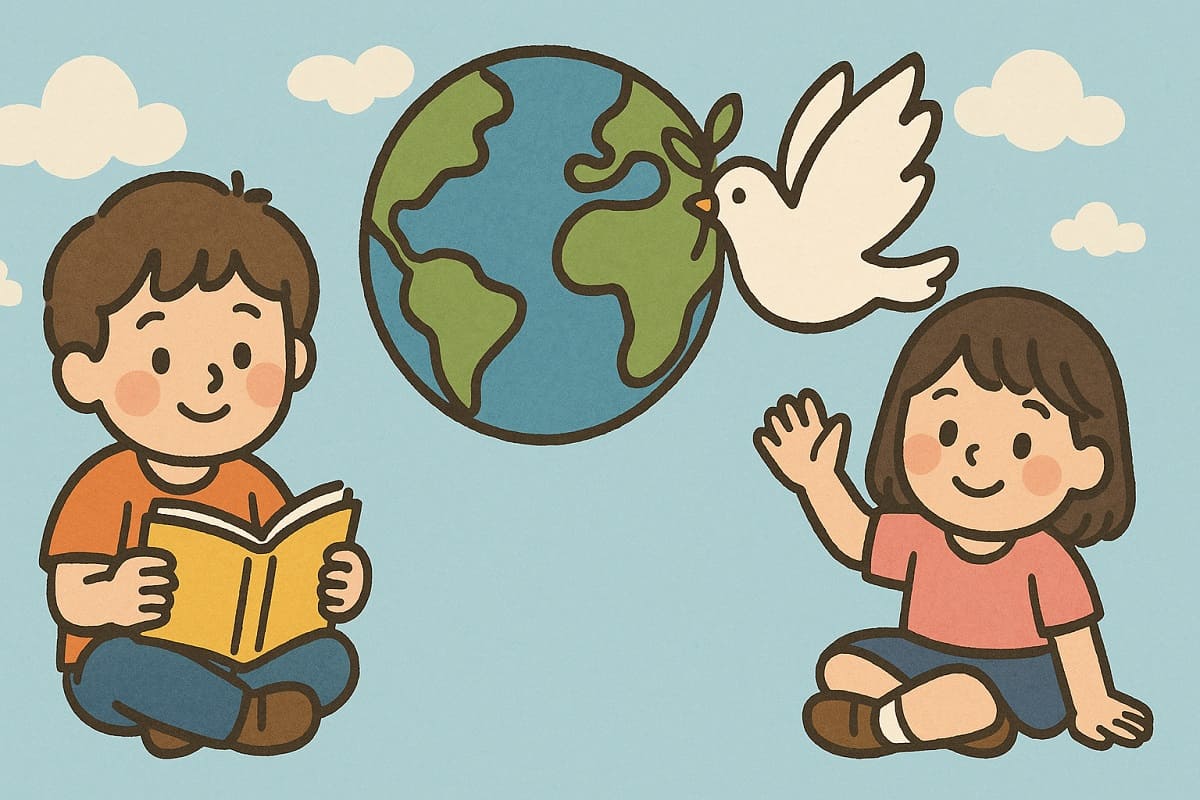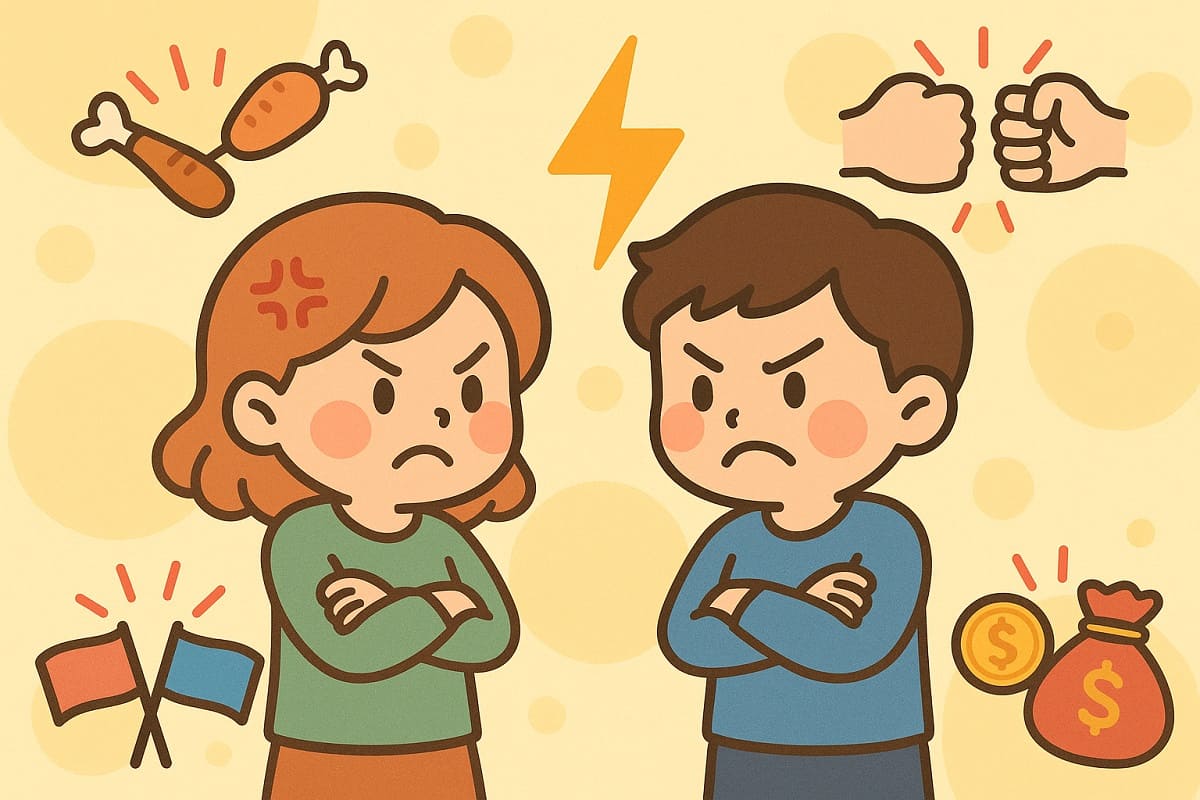同じ種族同士で殺し合いをするのは人間だけなの?

「戦争」や「殺人」という言葉を聞くと、多くの人が「人間って残酷だな」と感じるかもしれません。実際、同じ人間同士で争ったり、時には命を奪い合うことさえある現実は、ニュースでもたびたび目にします。
でも、ふと疑問に思ったことはありませんか?
「同じ種族同士で殺し合いをするのは、人間だけなの?」
この問いに答えるために、今回は心理学や動物行動学、進化生物学といったさまざまな学問の視点から、人間と他の動物がなぜ、どんな理由で同族を殺すのかについて、できるだけわかりやすく紹介していきます。
動物が同族を殺す理由とは?
実は、人間以外の動物でも同族殺しは珍しくありません。動物が仲間を殺す理由は、いくつかのパターンに分けられます。
① 交尾相手をめぐる争い
多くの動物のオスたちは、メスとの交尾のチャンスを得るために激しく競い合います。その過程で、ライバルを攻撃したり、時には殺してしまうこともあります。これは「生き残ったものだけが子孫を残せる」という自然界の厳しいルールに従っているのです。
② 縄張りの防衛
動物には自分のテリトリー(縄張り)を守る習性があります。他の個体が侵入してくると、激しく攻撃し、殺してしまうこともあるのです。ライオン、オオカミ、チンパンジーなど、群れで暮らす動物では特によく見られます。
③ 子どもを守る、または他の子を殺す
自分の子どもを守るために、他の親の子を殺すという行動もあります。あるいは、ライオンのように、新たに群れを乗っ取ったオスが、前のオスの子どもを殺すことも。これは、自分の子孫を残しやすくするための戦略です。
④ 食料として殺す(共食い)
中には、同じ種の仲間を食べてしまう動物もいます。ハムスターなどで見られる共食いは、ストレスや食料不足が原因とされることもあります。
つまり、動物の同族殺しには、生き残りや繁殖といった“自然な理由”があるのです。
人間が同族を殺す理由は?
では、人間はなぜ人間を殺すのでしょうか?動物のように単純な理由だけでは語れません。人間の場合、心理的・社会的・文化的な要因が複雑に関係しています。
① 怒りや復讐
人間は感情を強く持つ生き物です。怒りや恨み、復讐心によって相手を殺してしまうことがあります。これはチンパンジーのような霊長類にも見られますが、人間はより計画的にそれを行うことができるのです。
② 利益や権力の争い
戦争や殺人は、お金、土地、権力、地位などを手に入れるために起こることもあります。個人のレベルでは金銭トラブルや地位争い、国のレベルでは資源の奪い合いなどがそれにあたります。
③ 集団のため、という正当化
人間は「これは正しい戦いだ」と信じて戦うことができます。宗教や政治、民族意識、正義感などを理由に「敵を攻撃することは仕方がない」と考えてしまうのです。これは、言葉や文化、信念といった人間独自の力によって可能になることです。
人間は「冷静に殺せる」?
ある心理学の研究によると、人間の攻撃には2種類あるとされています。
- 反応的攻撃:カッとなって怒ってしまう攻撃(例:ケンカ)
- 先制的攻撃:冷静に計画して行う攻撃(例:計画的殺人や戦争)
チンパンジーは、感情に任せた反応的な攻撃が多いとされますが、人間は冷静に計画して攻撃する傾向が強いというのです。
でも、抑える力もあるのが人間
「冷静な攻撃」なんて聞くと、「人間ってすごく残酷じゃないか」と思ってしまうかもしれません。
でも安心してください。
人間には相手を思いやる心や、暴力を抑えるための法律や道徳もちゃんとあるのです。
たとえば、誰かが悪いことをしたとしても、すぐに暴力で解決するのではなく、裁判で判断したり、話し合いで解決しようとする力も人間にはあります。
また、「共感する心」や「罪悪感」といった、他人を大切にする感情も発達しています。これらの感情は、他の動物にも少しはありますが、人間の方がずっと強く感じることができます。
つまり、人間には“争いの力”と“平和の力”の両方があるのです。
人間と動物の違いはどこにある?
動物も人間も、同じ仲間を攻撃してしまうことがあります。でも、その理由ややり方、考え方には大きな違いがあります。ここでは、人間と動物の違いをわかりやすく5つにまとめて紹介します。
① 道具や武器を使う力
人間は、石や木を使った道具から、ナイフや銃、さらにはミサイルや核兵器まで、いろいろな「武器」を自分で作って使うことができます。これによって、遠くの相手を安全な場所から攻撃することもできるようになりました。
チンパンジーなどの動物も道具を使うことはありますが、戦いのために道具を使ってチームで戦うようなことは、基本的にはしません。そういう意味では、人間のほうがずっと進んだ「攻撃の方法」を持っているといえます。
② 言葉と文化の力
人間は「言葉」で気持ちや考えを伝えあい、「文化」をつくって生きています。たとえば、誰かを「悪い奴」だとみんなに伝えて戦わせたり、反対に「戦ってはいけない」と教えたりすることもできます。
宗教や法律、国のルールなども、人間の文化の一部です。こうした文化があるからこそ、人間は大きな戦争をおこしたり、反対に平和を守ったりすることができるのです。動物にはこうした文化はありません。本能や習慣で動いています。
③ 思いやりとルールの心
人間は、他の人の気持ちを考えたり、「これは悪いことだ」と感じたりする心を持っています。たとえば、「あの人が苦しんでいるのはかわいそう」と思ったり、「うそをつくのはよくない」と思ったりするのがその例です。
また、「ルールは守らなきゃいけない」と思う気持ちや、「ルールをやぶった人には罰を与えるべきだ」と感じる“正義感”もあります。動物にも仲間にやさしくする行動はありますが、こうしたルールや正義の気持ちは、人間ほどはっきりとは見られません。
④ 抽象的なことを考える力
人間は、目に見えないことも頭の中で考えて作り出すことができます。たとえば、「国」や「人種」、「宗教」といった考え方です。こうした「実体がないもの」のために争ったり、命をかけたりすることができるのは人間だけです。
動物たちは、目の前の食べものや縄張り(土地)など、はっきりとした理由があるときに争います。「この土地はうちのものだ」といった感覚はあっても、「国や宗教のために戦う」といった考え方は持っていません。
⑤ 大きな社会をつくる力
人間は、何百人、何千人、時には何億人という大きな集まり(国や社会)をつくって生きています。そして、その中でリーダーがいて、ルールがあって、時には軍隊があって…と、しっかりしたしくみで動いています。
動物にも群れはありますが、多くは数十頭ほどの小さな単位です。強いオスが群れをまとめることはあっても、人間のような大規模な国家のしくみはありません。
人間と動物は、「同じ種族同士で争うことがある」という点では共通していますが、そのやり方や考え方にはこれだけのちがいがあるのです。
おわりに
最後に、もう一度この問いに答えてみましょう。
「同じ種族同士で殺し合いをするのは人間だけなの?」
答えはこうです。
いいえ、人間だけではありません。他の動物でも、同じ種の仲間を殺すことはあります。
でも、人間はその争いを“計画的に”“大規模に”“正当化して”行えるという点で、ほかの動物とは違うのです。
そして、人間には争いをやめる力もあるということを、忘れないでほしいと思います。
主な参考文献
Gómez, J. M. et al. (2016). The phylogenetic roots of human lethal violence. Nature, 538, 233–237.
Gómez, J. M. et al. (2021). Killing conspecific adults in mammals. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 288, 20211080.
Wrangham, R. W. (2017). Two types of aggression in human evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 1325–1330.
Wrangham, R. W. (2024). Targeted conspiratorial killing, human self-domestication and the evolution of groupishness. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 379, 20200445.
Rosenbaum, S. et al. (2016). Observations of severe and lethal coalitionary attacks in wild mountain gorillas. Scientific Reports, 6, 37018.