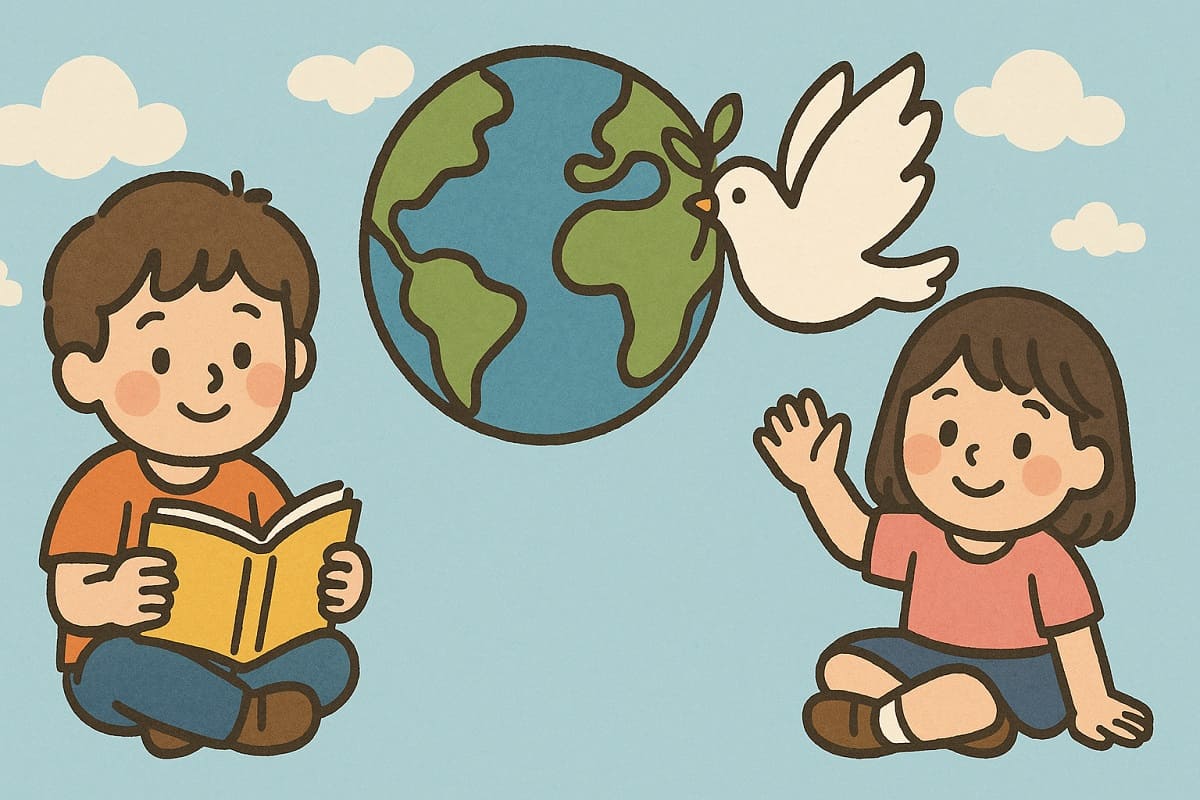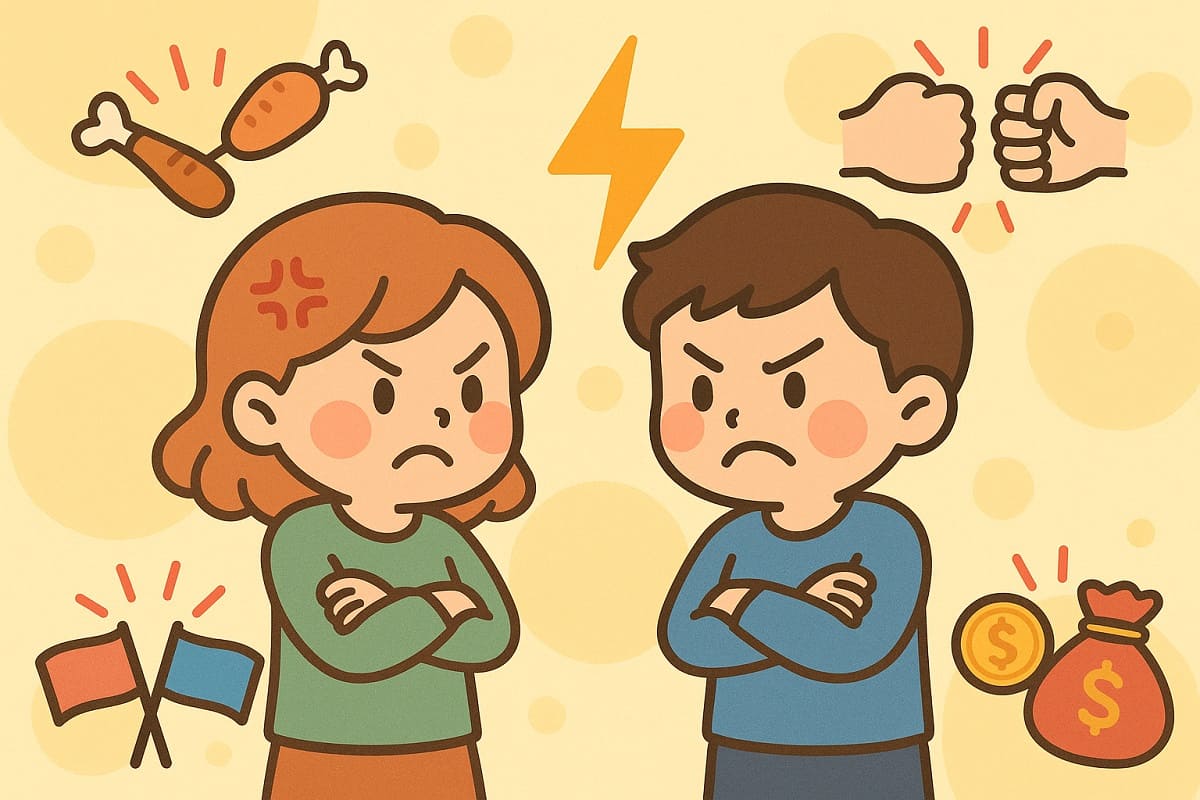人はどうして戦争で人を殺せるの? 兵士たちの心理を知ろう

ニュースや映画で「兵士が戦争で敵を撃ち殺す場面」を見たことがある人は多いでしょう。でも、よく考えてみると、「人を殺す」なんて普通は絶対にしてはいけない行為です。それなのに、どうして戦争ではそれが行われてしまうのでしょうか?
今回は、実際に兵士たちが「引き金を引いて人を殺す」までに、どんな心理状態になるのか、なぜそれが可能になるのかを、できるだけわかりやすく説明します。
本当は「人を殺したくない」のが普通
実は、ほとんどの人間は本能的に「人を殺すこと」に強い抵抗を感じます。たとえば第二次世界大戦のころの研究では、戦場で銃を持っていても、敵に向けて発砲しなかった兵士がたくさんいたそうです。人間は、目の前の相手が「同じ人間」だと感じてしまうと、引き金を引けなくなるのです。
敵を「人間ではない」と思い込む
でも、戦争ではそんなふうに迷っていたら、自分が殺されてしまいます。だから、軍隊では兵士たちに「敵を人間として見ないようにする訓練」を行います。
たとえば、
- 「敵は虫や化け物だ」
- 「あれは人間じゃなくて“ターゲット”だ」
というように、相手を“非人間化”するのです。
このように考えることで、兵士は罪悪感を持たずに攻撃できるようになります。
「命令だから仕方ない」と思う
次に重要なのが「命令への服従」です。1960年代にアメリカの心理学者スタンレー・ミルグラムが行った実験では、「権威ある人から命令されると、人は良心に反してでも命令に従ってしまう」ことが分かりました。
軍隊では、上官の命令は絶対です。たとえその命令が「人を殺せ」というものであっても、「命令だから」と思うことで、自分の行為への責任を感じにくくなります。
「仲間のため」に戦う
実は、兵士が戦場で殺人行動に出る最大の理由のひとつは、「国のため」ではなく「仲間のため」と言われています。
兵士たちは小さな部隊で行動し、毎日一緒に寝起きし、訓練し、命を預け合う存在になります。そんな中で、「自分が撃たなかったら、隣の仲間が死ぬかもしれない」と思うと、迷っている余裕なんてなくなってしまうのです。
このように、「仲間を守るために撃つ」という考え方が、兵士の心を支えているのです。
「訓練」で殺すことに慣れさせる
現代の軍隊では、兵士に「殺すための訓練」をしています。たとえば、人型の的を使って射撃練習をしたり、反射的に撃つように体に覚えさせるような方法です。
こうした訓練により、兵士は「人を撃つ」という行動を、感情ではなく反射で行うようになります。「これは訓練の続きだ」と思うことで、実際の殺人に対する心理的な抵抗が弱まってしまうのです。
殺したあとの心の傷「道徳的な傷」
戦争が終わったあと、多くの兵士たちは「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」に苦しみます。爆撃の音や死体の映像がフラッシュバックして、眠れなくなったり、不安になったりするのです。
しかし最近では、それとは別に「モラル・インジュリー(道徳的な傷)」という新しい考え方も注目されています。これは「自分がやったことが間違っていたのではないか」と思い、自分自身を許せなくなる心の状態のことです。
たとえば、
- 民間人を間違って撃ってしまった
- 無抵抗な人を命令で殺してしまった
- 殺人を喜んでいた自分に気づいた
こうした経験は、兵士にとって深い罪悪感や自己否定につながり、長年にわたって苦しみ続けることもあります。
戦争の「本当のコスト」
戦争では、多くの命が奪われるだけでなく、生き残った兵士の心も壊れてしまうことがあります。兵士は命令に従い、仲間を守り、自分を守るために人を殺します。でもそのあとに「なぜ自分はあんなことをしたのか」と、自分自身に問い続けるのです。
戦争が終わっても、兵士の心の中では「戦い」が終わらないことがある。それが戦争の“見えないコスト”なのかもしれません。
まとめ
人が戦場で人を殺せるようになる背景には、さまざまな心理的な仕組みがあります。
- 敵を「人間ではない」と思い込む
- 「命令だから」と責任を手放す
- 仲間のために戦う
- 訓練で反射的に撃つようにされる
- その後、深い心の傷を負う
私たちが平和な社会で暮らしている今こそ、戦争に行く兵士たちの「心のリアル」に目を向けることが大切です。そして、「なぜ戦争が起きるのか」だけでなく、「なぜ人は人を殺せるのか」という問いに向き合うことが、未来の平和への一歩になるかもしれません。
主な参考文献
- デーヴ・グロスマン. (2004). 戦争における「人殺し」の心理学. ちくま学芸文庫.
- Litz, B. T., et al. (2009). Moral injury and moral repair in war veterans: A preliminary model and intervention strategy. Clinical Psychology Review, 29(8), 695–706.
- Milgram, S. (1974). Obedience to authority: An experimental view. New York: Harper & Row.
- Shay, J. (1994). Achilles in Vietnam: Combat trauma and the undoing of character. New York: Scribner.
- 香山リカ. (2010). イラク戦争帰還兵のPTSDはなぜ多いのか? imidas–情報・知識&オピニオン.