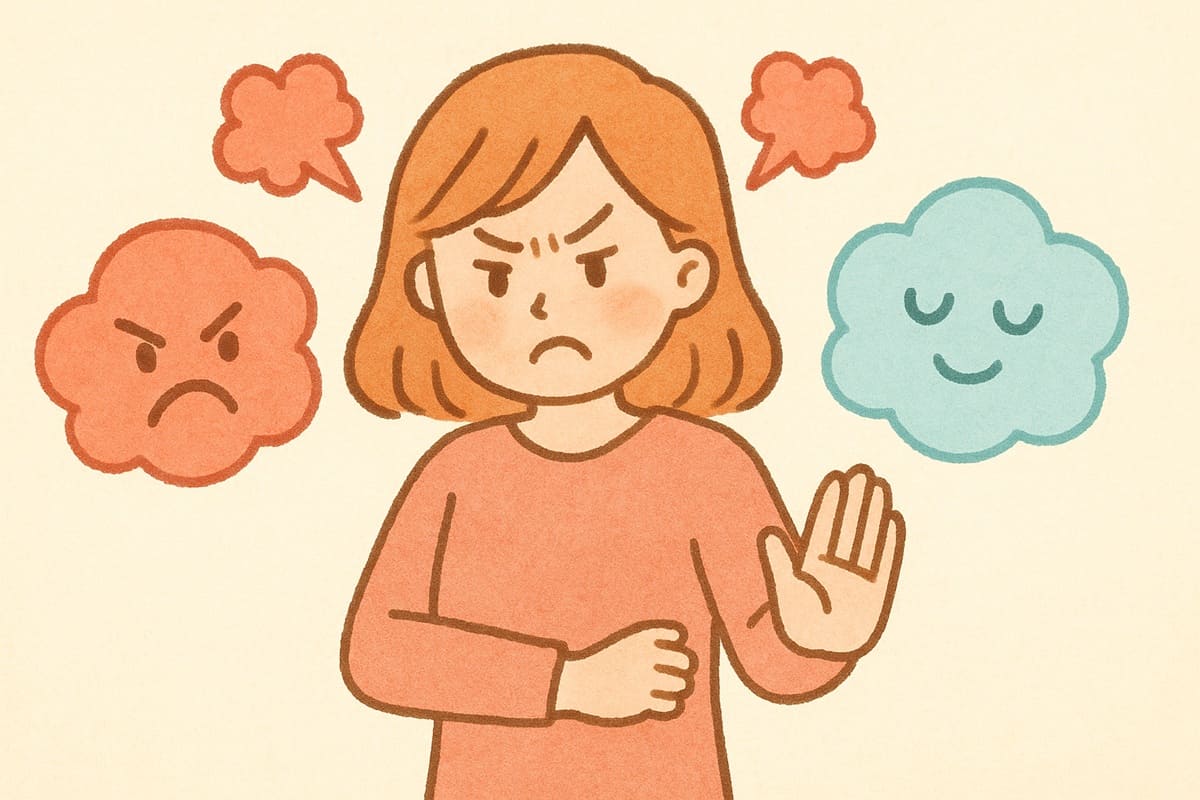人はなぜ争うの? 「バランス・オブ・パワー」の仕組みを知ろう

ウクライナや中東、台湾周辺など、今も世界のどこかで国と国の間に緊張が走っています。
そんなニュースを見るたびに、
「どうして人間は争いをやめられないの?」
と思いますよね。
今回は、国際政治の世界でよく使われている「バランス・オブ・パワー(力の均衡)」という考え方を紹介しながら、「人と人、国と国がなぜ争うのか」「どうすれば争いを防げるのか」を一緒に考えてみましょう。
「バランス・オブ・パワー」ってなに?
「バランス・オブ・パワー」は、国際政治でよく使われる言葉で、直訳すると「力の均衡」という意味です。
具体的には、一つの国が強くなりすぎないように、他の国々が協力してその力を抑えようとする仕組みのこと。
たとえば、ある国がどんどん軍事力を増やし、周辺国を脅かすようになったら、他の国は「これは放っておけない」と思います。
そこで他の国々は、お互いに協力したり、自分たちの軍事力も増やしたりして、その国に対抗しようとするのです。
こうすることで、「どこか一国だけが圧倒的に強くなって戦争を起こすリスクを減らす」ことができると考えられています。
このような「パワーバランス」の仕組みが、争いを防ぐ安全装置になるというのが、バランス・オブ・パワー理論です。
本当に戦争を防げるの?
この理論は、一見すると「とても合理的」な考えに見えます。
でも実際には、「争いを防ぐためのパワーバランス」が、逆に「争いの原因」になることもあるのです。
たとえば、ある国が軍事力を増やしたとき、周りの国も不安になって自分たちも武器を増やす。
すると、さらに最初の国が警戒して、もっと武器を増やす……。
こんなふうにお互いが疑い合って軍備をどんどん増やしてしまう現象を「軍拡競争」と言います。
バランスを保つはずの仕組みが、かえって緊張を高め、戦争のリスクを上げてしまうことがあるのです。
冷戦時代のバランス・オブ・パワー
この理論が特に注目されたのが、第二次世界大戦後の「冷戦時代」です。
当時、アメリカとソ連という二つの超大国が、世界の覇権をめぐって対立していました。
お互いに「相手に負けないように」と軍事力を高め、特に核兵器の開発と配備を競い合いました。
その結果、お互いがいつでも相手を壊滅させられるだけの核兵器を持つようになります。
この状態は「相互確証破壊(Mutually Assured Destruction, MAD)」と呼ばれています。
どちらかが核を使えば、もう一方も必ず反撃する。だから、どちらも手を出せないのです。
つまり、「バランス・オブ・パワー」によって、恐怖による平和が保たれていたと言えるでしょう。
しかし、実際にはベトナム戦争やアフガニスタン紛争など、両陣営が直接ぶつからない「代理戦争」は世界各地で起きており、緊張は常に高い状態にありました。
現代にも残るバランスの考え方
この「力の均衡」の考え方は、今の世界にも残っています。
たとえば、近年の中国の急成長に対して、アメリカや日本、インド、オーストラリアなどが連携を強めています。
「クワッド」と呼ばれるこの枠組みは、中国が軍事的にも経済的にも影響力を広げることに対して、他の国々が「バランスをとろう」とする動きの一例です。
また、アメリカは北大西洋条約機構(NATO)を通じて、ロシアとの均衡も維持しようとしています。
このように、ある国の力が強くなりすぎることにブレーキをかけるという考え方は、現代の国際政治でも重要な役割を果たしているのです。
軍拡競争を防ぐための取り組み
でも、力のバランスだけに頼ると、軍拡競争になってしまうこともあります。
「相手が軍事力を増やすなら、自分たちも負けないようにしよう」と、どんどん武器が増えていくのです。
では、そんな悪循環を止めるにはどうしたらいいのでしょうか?
① 軍縮条約
アメリカとソ連(後のロシア)は、冷戦中やその後、戦略兵器削減条約(START)などの軍縮条約を結び、核兵器の数を制限しました。
こうした条約は、お互いに「ちゃんと武器を減らしている」という信頼を築くためのルールです。
② 信頼醸成措置
これは、「お互いに誤解しないように、情報をあらかじめ伝える」ための取り組みです。
たとえば、「これから軍の訓練をするよ」と事前に相手に通知することで、「まさか攻撃じゃないよね!?」という疑いを防ぐことができます。
冷戦時代のヨーロッパでは、こうした取り組みが進みました。今では、アジアや中東でも少しずつ広がってきています。
③ 国際機関の活用
国連やASEANなどの国際機関も、対話の場をつくったり、武器の拡散を防いだりする役割を担っています。
「核拡散防止条約」は、核兵器が新たに広まらないようにするための重要な取り組みのひとつです。
おわりに:本当の平和をつくるには
「バランス・オブ・パワー」は、戦争を防ぐための一つの手段です。
でも、それはあくまで「力」で保たれた平和であり、いつ崩れるかわからない危うさも含んでいます。
大切なのは、力に頼りすぎないこと。
お互いに信頼し合い、話し合い、武器ではなく言葉で解決する文化を育てていくことです。
私たち一人ひとりが世界の情勢に関心をもち、争いのない未来を想像すること。
それもまた、平和への一歩になるのではないでしょうか。