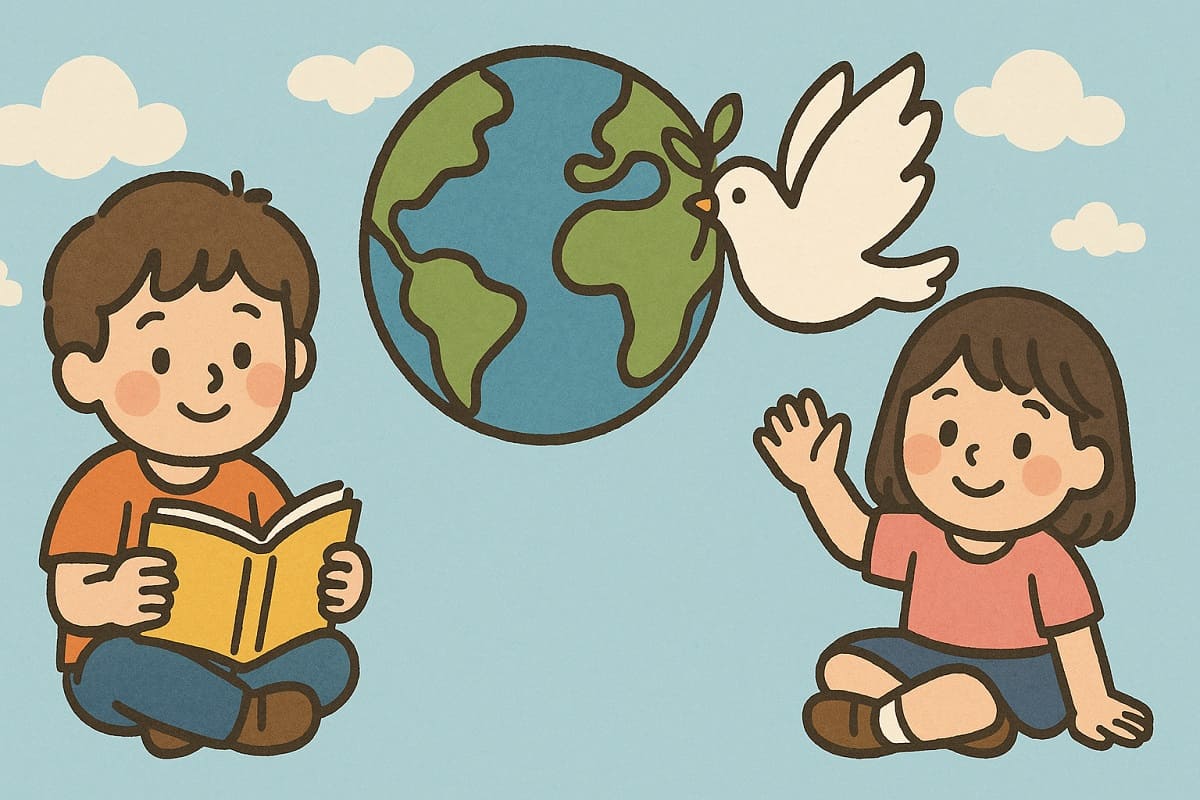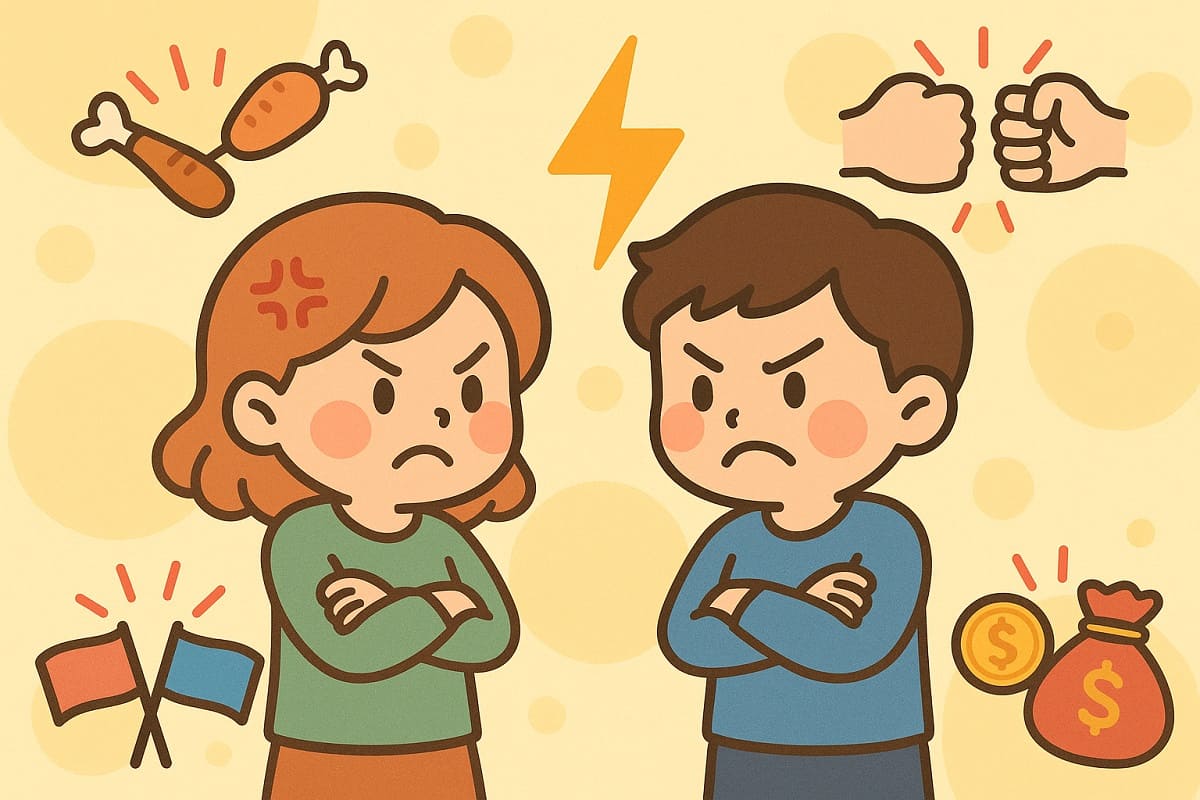いじめはなぜ起こるの? 学校でいじめが起きる原因と対策を知ろう
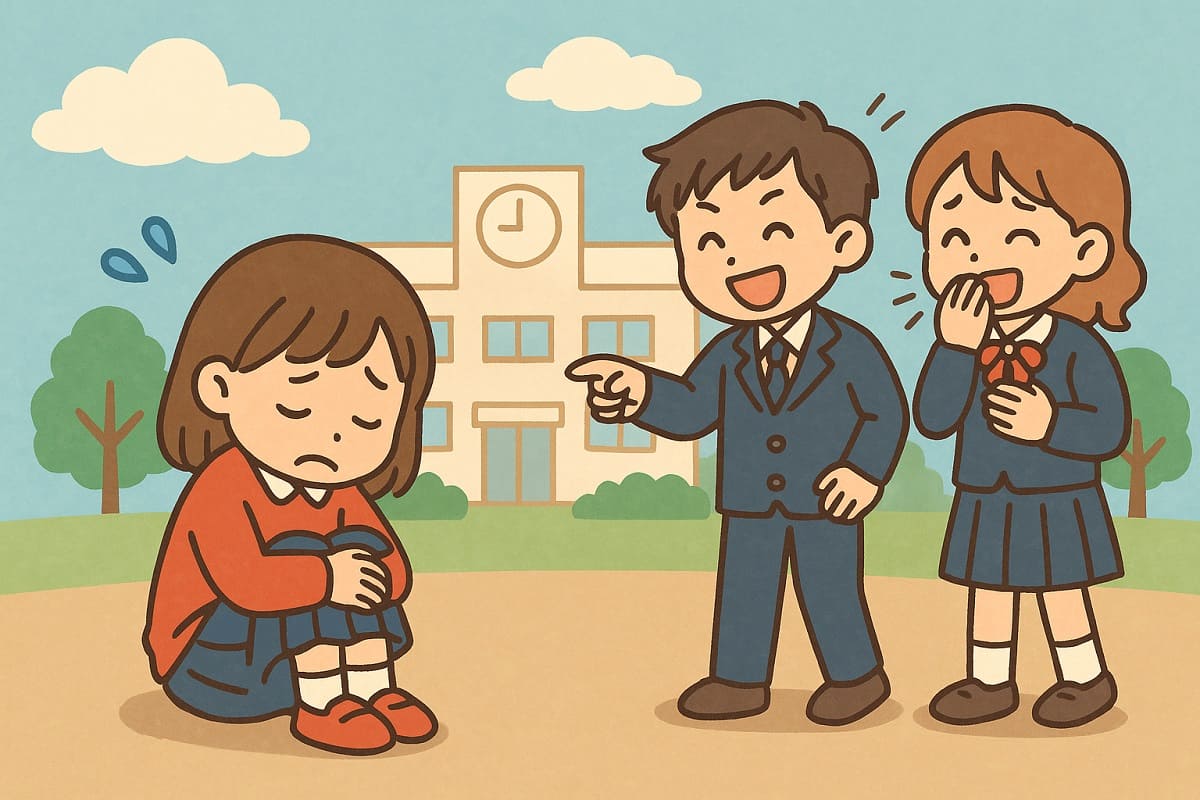
「いじめ」は、誰にとっても身近な問題です。ニュースやSNSでも、いじめに関する話題をよく見かけますよね。自分がいじめられていなくても、友だちやクラスの誰かがつらい思いをしているのを見たことがある人もいるのではないでしょうか。
いじめは、人の心を深く傷つける行為で、ときには命に関わる深刻な問題にもなります。でも、そもそもいじめはなぜ起こるのでしょうか? そして、どうすればいじめを減らすことができるのでしょうか?
この記事では、文部科学省や大学の研究に基づいて、「いじめが起こる原因」と「私たちにできる対策」について、わかりやすく解説していきます。
いじめは増えている?
文部科学省の調査によると、2023年度に日本全国の小・中・高校などで確認されたいじめの件数は、なんと73万件以上でした。これは過去最多の数字で、毎年のように増えています。さらに、いじめによって心や体に大きな傷を負ってしまった「重大事態」は1300件以上起きていて、とても深刻な状況です。
「どうしてこんなに多いの?」と思うかもしれませんが、実は最近では先生たちがいじめを積極的に見つけようとしていたり、生徒アンケートを定期的に行ったりするようになっているため、「隠れていたいじめが見えるようになった」という側面もあります。
とはいえ、いじめ自体がなくなっているわけではありません。特に最近では、スマホやSNSの使い方が原因でトラブルが起きるケースも増えてきています。
原因① SNSやネットいじめの広がり
スマートフォンの普及によって、LINEやInstagram、XなどのSNSが多くの中高生にとって当たり前のコミュニケーション手段になりました。でも、この便利なツールが「いじめの場所」にもなってしまうことがあります。
たとえば、グループLINEで仲間外れにされたり、悪口を書かれたり、ひどいときは写真や個人情報が勝手にネットに流されたりします。こうしたネットいじめは、学校の外でも起きるため、「いつでもどこでもいじめが続く」という恐ろしさがあります。
しかも、SNSの世界では匿名で書き込むことができるため、相手を特定しにくく、先生や保護者が気づきにくいのが問題です。ネットいじめの被害は、精神的なダメージがとても大きく、最悪の場合は自殺につながってしまうこともあります。
原因② 家庭環境や親との関係
実は、「家庭での過ごし方」や「親との関係」も、いじめに影響を与えることがあります。
ある研究によると、親とあまり話さない子どもや、家庭で暴力を受けている子どもは、いじめの被害者にも加害者にもなりやすいことがわかっています。たとえば、親から大切にされていないと感じている子は、自分に自信が持てず、友達とうまく関われなかったり、逆に誰かをいじめることでストレスを発散しようとしてしまうこともあるのです。
また、家庭が経済的に苦しいと、周りと比べて持ち物や服が違ってしまい、からかわれたり仲間外れにされたりする原因にもなります。お金の問題は子ども本人に責任はないのに、それがいじめにつながってしまうのは本当に悲しいことですよね。
原因③ 学校の空気や先生の対応
いじめは「特定の子どもが悪い」から起きるわけではありません。実は、学校やクラスの雰囲気も大きな影響を持っています。
たとえば、クラスの中に「変わっている子を笑いものにする空気」があったり、「目立つ子を引きずり下ろそうとする雰囲気」があったりすると、いじめが起こりやすくなります。日本の学校は「みんなと同じであること」が大事にされがちなので、少しでも違う子がいると、その子が「浮いている」と感じられ、いじめの対象になることがあります。
また、先生がいじめに気づかない、または対応が遅れると、いじめがどんどん悪化してしまうこともあります。担任の先生だけに任せるのではなく、学校全体でチームとして対応できる体制が必要です。
対策① クラス全体で「いじめはダメ」と伝える
いじめをなくすためには、まずクラスの雰囲気を変えることが大切です。先生が一方的に怒るのではなく、生徒たち自身が「いじめはかっこ悪い」「やめよう」と思えるような雰囲気を作ることがポイントです。
実際に、海外の学校では、クラス全体で話し合いをしたり、傍観者(見ているだけの人)が止めに入るようなトレーニングをすることで、いじめが大幅に減ったという事例もあります。
対策② 小さなサインを見逃さない
いじめが大きな問題になる前に、小さなサインを見つけることがとても大事です。
たとえば、「最近、あの子が元気ないな」と思ったら、何気なく話しかけてみたり、相談室に行ってみたりするのも一つの手です。自分がいじめられているときも、「誰かに話すこと」はとても大切です。相談できる大人がいないと感じたら、SNS相談窓口や24時間子供SOSダイヤルなども活用してみてください。
対策③ 家庭や地域、社会全体で支える
いじめは、学校だけで解決できる問題ではありません。家庭や地域社会、大人全体の意識が変わることも必要です。
たとえば、親が子どもにちゃんと関心を持ち、話を聞くこと。地域の人たちが登下校を見守ったり、困っている子に声をかけたりすること。こうした小さな行動が、子どもたちを守る大きな力になります。
また、国や自治体も、いじめをなくすためにさまざまな制度や法律を整えています。最近では「こども家庭庁」という新しい機関もでき、いじめ対策が社会全体の課題として考えられるようになってきました。
おわりに
いじめは、誰にとっても他人事ではありません。いじめる人も、いじめられる人も、そして見ている人も、実はみんな関係しています。
大切なのは、「いじめは絶対にダメ」「見て見ぬふりをしない」という意識を、みんなが持つことです。一人ひとりができることは小さいかもしれませんが、みんなの行動が集まれば、大きな力になります。
この記事が、いじめについて考えるきっかけになれば幸いです。
主な参考文献
- 中村豊, 日野陽平. (2024). 児童生徒いじめの重大事態化を防止する効果的実践モデルの開発に関する基礎研究. 東京理科大学教職教育研究, 9, 13–22.
- Nishida, A. (2010). 思春期・青年期の「いじめ」に影響を与える家庭関連要因の検討. Human Developmental Research, 24, 147–154.
- 梶原豪人. (2023). 子どもの所有物の欠如といじめ被害の関連に関する実証分析. 社会政策, 16(1), 252–263.
- OECD. (2015). How’s Life? – Measuring Well-being. OECD Publishing.
- 文部科学省. (2024). 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(速報値).