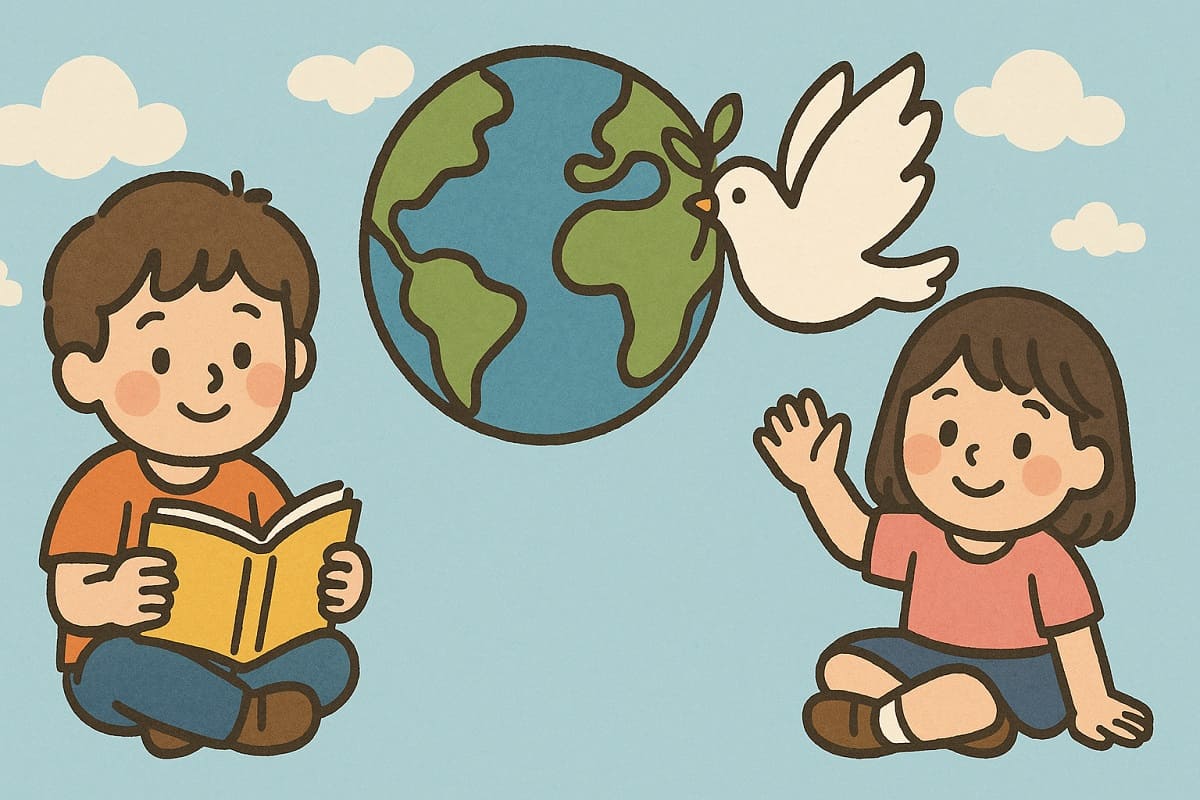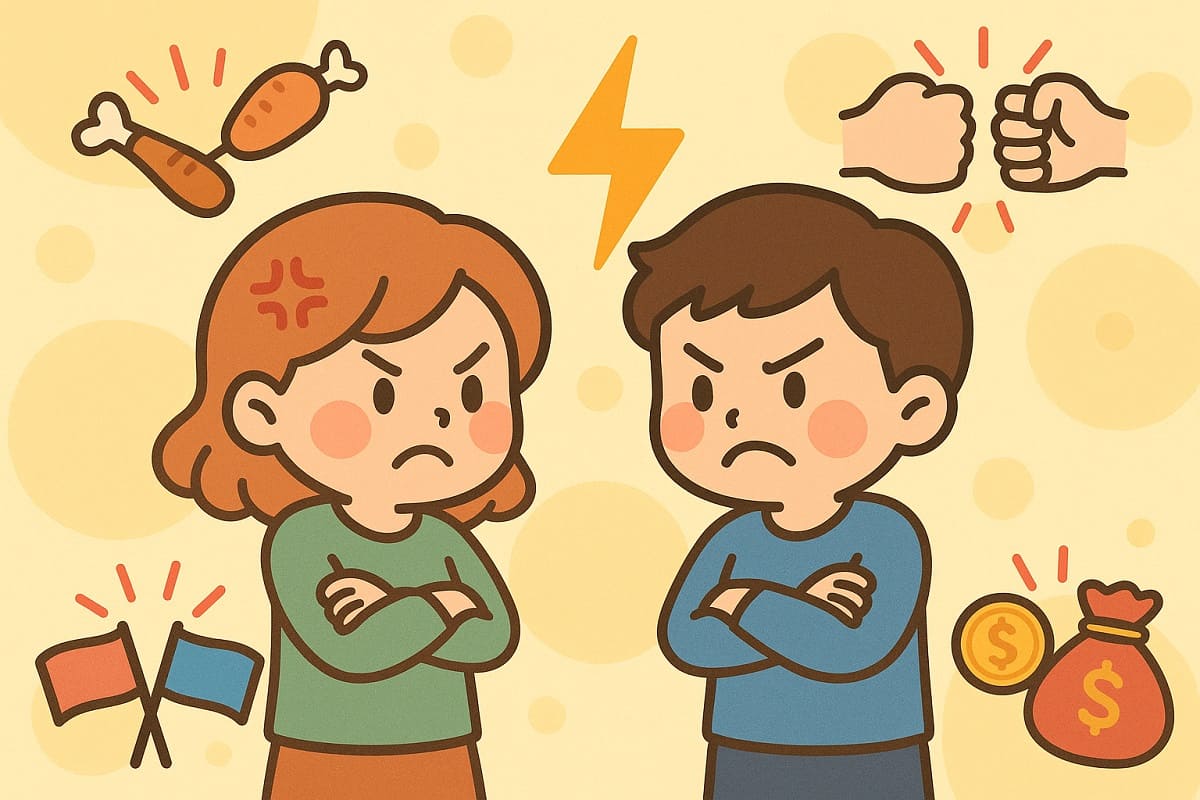人はなぜ争うの? 限りある資源の奪い合い

「戦争」や「紛争」と聞くと、多くの人は宗教や民族の違い、政治的な対立を思い浮かべるかもしれません。でも実は、私たちの生活に深く関わる“資源”をめぐって争いが起こることも、世界ではたくさんあります。
資源とは、たとえば水、石油、土地、鉱物など、生活や産業に欠かせないもの。これらの資源が「限りあるもの」だからこそ、それを「めぐる争い」が起こることがあります。今回は、「資源の奪い合い」が原因で起きた争いについて、できるだけわかりやすく紹介します。
どんな資源を人は奪い合ってきたの?
人類の歴史を振り返ると、次のような資源が原因で争いが起こってきました。
水
水は人が生きるうえで欠かせない資源です。地球上の水のほとんどは海水で、農業や飲み水に使われる“淡水”(塩分を含まない水)は、全体のたった約2.5%しかありません。
淡水は多くの国が共有していて、たとえば、インドとパキスタンが使っているインダス川では、水の使い方をめぐって長い間争いがありました。現在は「インダス条約」という約束ごとで水の分け方を決めて、戦争を防いでいます。
石油・天然ガス
石油は車や工場、飛行機を動かすための大切なエネルギー資源です。特に中東の国々では石油がたくさんとれるため、それを狙った戦争が何度も起きています。
たとえば、1990年にイラクがクウェートに攻め込んだ湾岸戦争は、クウェートの豊かな石油資源が原因のひとつとされています。また、イランとイラクのあいだで起きた戦争(1980〜1988年)も、石油がたくさん出る土地の取り合いが背景にありました。
金属・鉱物(ダイヤモンドやコルタンなど)
スマートフォンやパソコンに使われる「コルタン」や、美しい「ダイヤモンド」なども、争いの原因になることがあります。たとえばアフリカのシエラレオネやコンゴでは、武装グループがダイヤモンドや鉱物を違法に売って、武器を買うためのお金にしてきました。こういった資源は「紛争鉱物(ふんそうこうぶつ)」と呼ばれています。
土地や農地
良い農地や水が手に入る土地も、大きな争いの原因になります。特に、アフリカのスーダンにあるダルフール地方では、土地と水を求めて農民と遊牧民が争いになり、大きな内戦にまで発展しました。気候変動や砂漠化の影響で、使える土地が減っていることも問題です。
実際に起こった「資源をめぐる争い」
ここでは、実際に資源をめぐって起こった戦争や紛争の例をいくつか紹介します。
- 湾岸戦争(1990–1991年)
イラクがクウェートに侵攻。理由のひとつは、クウェートが石油をたくさん持っていたこと。 - スーダン内戦(1983–2005年)
南スーダンで石油が見つかり、それが原因で南北の対立が激しくなりました。のちに南スーダンは独立しましたが、石油の分け方をめぐっていまも対立が続いています。 - ダルフール紛争(2003年〜)
スーダン西部のダルフール地方では、干ばつや砂漠化で使える土地や水資源が少なくなり、農民と遊牧民のあいだで土地をめぐる争いが起きました。気候変動も背景にあり、人道危機にまで発展しました。 - コンゴ民主共和国の紛争
コルタンという希少な金属が取れる鉱山をめぐって、多くの武装勢力が争っています。彼らは鉱山で得たお金を武器の購入に使い、戦争が終わらなくなっています。 - チャコ戦争(1932–1935年)
南アメリカのボリビアとパラグアイが、石油があるとされた土地「チャコ地方」をめぐって戦争を起こしました。
争いをなくすために、世界がしていること
では、こういった資源の争いを防ぐために、世界はどんな努力をしているのでしょうか?
水のルールを決める
インダス川のように、川を共有する国どうしが話し合って、「どうやって水を分けるか」を決める条約がたくさん結ばれています。こうした約束は戦争を防ぐ効果があり、これまで多くの国が武力ではなく話し合いで解決してきました。
紛争鉱物の取引を規制する
ダイヤモンドなどの資源が戦争の資金にならないように、「どこで採れたものか」を証明する制度もあります。「キンバリー・プロセス」という国際的な枠組みでは、紛争地からのダイヤモンドを国際市場から締め出す仕組みをつくっています。
また、スマートフォンなどに使われる金属についても、企業に「その資源がどこから来たのかを調べる責任」を求める法律がアメリカやヨーロッパでつくられました。
国際機関の仲介
国連や世界銀行などの国際機関が、資源をめぐる対立に対して話し合いの場を提供したり、ルール作りをサポートしたりしています。たとえば、インダス条約は世界銀行が仲介したことでも知られています。
おわりに
人は「自分たちにとって大切なもの」を守ろうとするとき、どうしても他の人とぶつかってしまうことがあります。水、石油、土地、鉱物―限られた資源をめぐる争いは、これからの時代にも続いていくでしょう。
でも、そのたびに「話し合う」「分け合う」ことができれば、争わずに済む道もあるはずです。国や民族の違いをこえて、資源をどう使っていくかをみんなで考えること。それこそが、平和への第一歩なのかもしれません。
主な参考文献
- Petersen-Perlman, J., Veilleux, J. C., & Wolf, A. T. (2017). International water conflict and cooperation: challenges and opportunities. Water International, 42(2), 105–120.
- U.S. Institute of Peace. (2004). Minerals and conflict. Washington, D.C.: USIP.
- United Nations Peacekeeping. (n.d.). Conflict and natural resources. United Nations.
- Carnegie Endowment for International Peace. (2012). Sudan: From conflict to conflict. Carnegie Endowment.
- Global Witness et al. (2008). Coltan, cell phones, and conflict: The war economy of the DRC. New Security Beat.