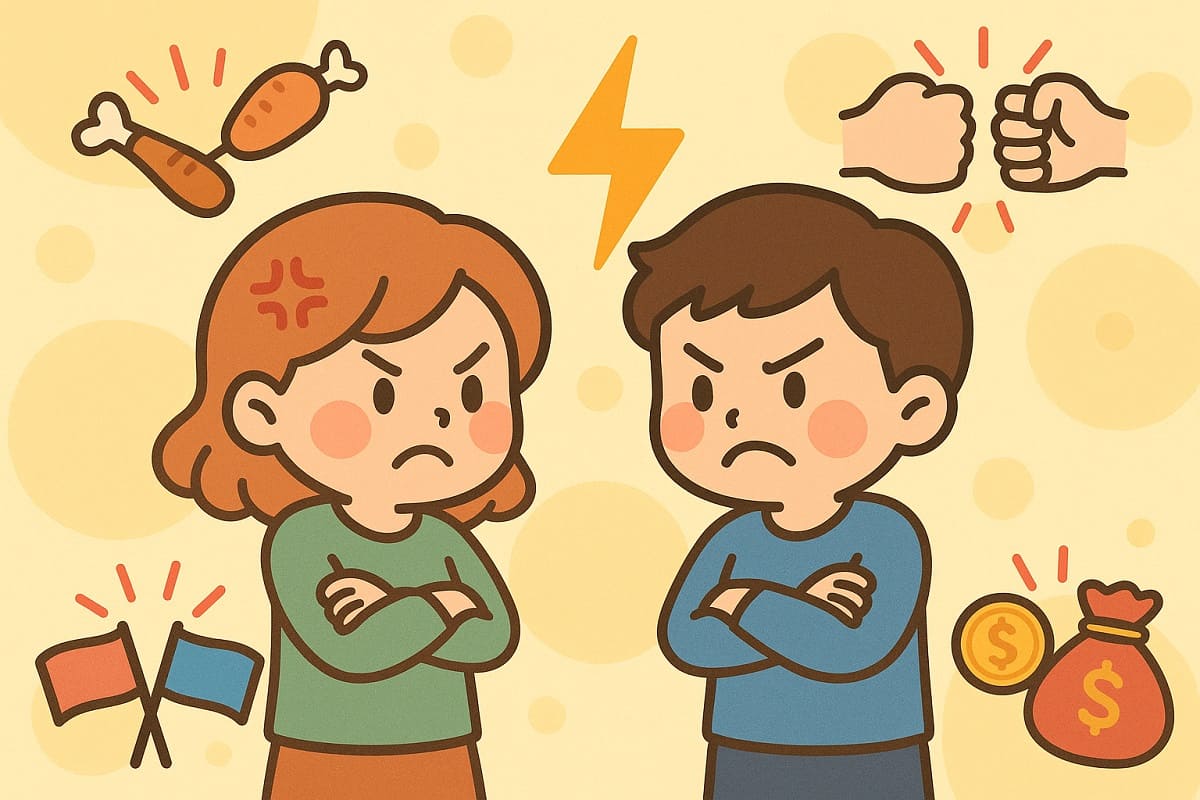平和教育ってなに? 「平和について学び、平和のために学ぶ」こと
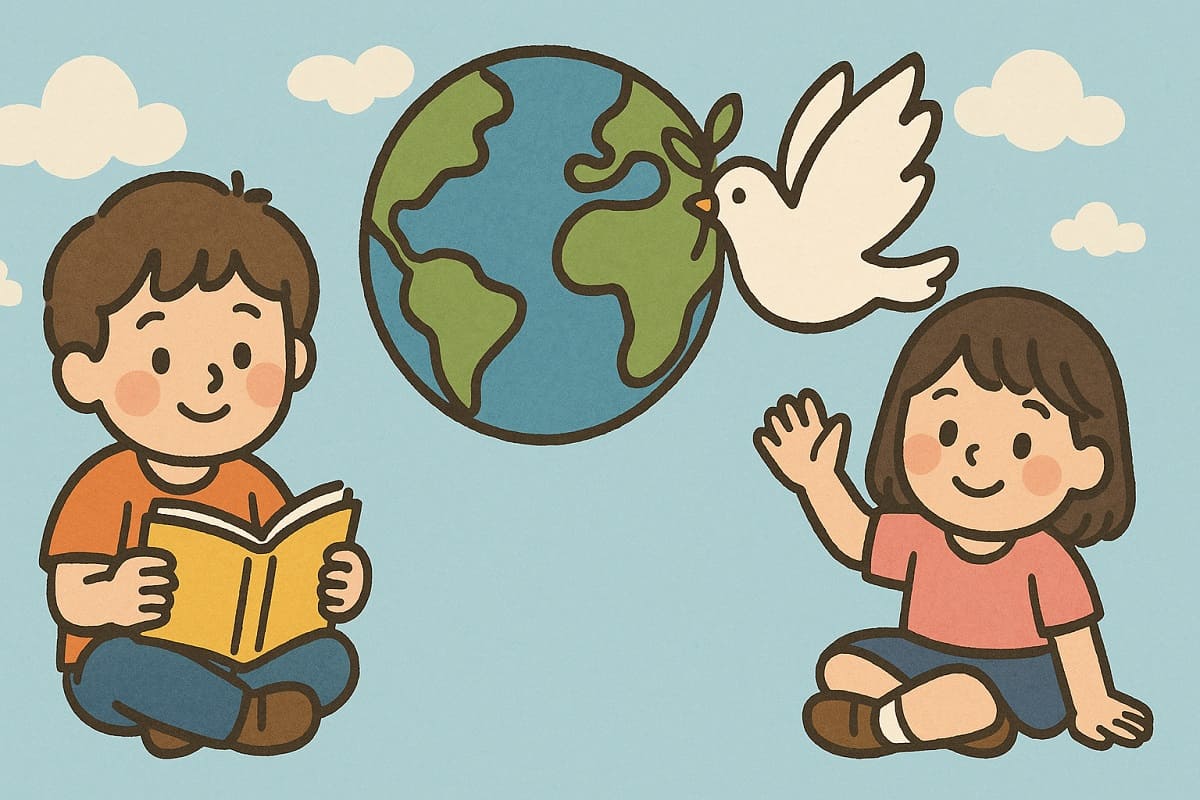
「平和な世界をつくりたい」—そんな願いを、あなたも一度は抱いたことがあるのではないでしょうか。
戦争や暴力、いじめや差別のない社会。それは決して夢物語ではありません。でも、そのためには、私たち一人ひとりが「平和」について学び、考え、行動できる力を身につけることが大切です。
そこで注目されているのが「平和教育」です。
でも、「平和教育って何を学ぶの?」「どうして大事なの?」と感じる人も多いと思います。この記事では、そんな疑問にわかりやすく答えていきます。
平和教育とは「平和について学び、平和のために学ぶ」こと
平和教育とは、簡単に言うと「平和について学び、平和のために学ぶ」ことです。
たとえば、戦争の歴史を知ることや、世界で起こっている紛争や貧困の問題について学ぶこと。
さらには、クラスでの話し合いや友達との関係づくりの中で、「どうやったらケンカせずに話し合えるか」「相手の気持ちを考えるにはどうすればいいか」といったことを学ぶのも、平和教育の一つです。
国連のユニセフ(UNICEF)は、平和教育を「子どもや若者、大人が暴力を予防し、問題を平和的に解決し、よりよい社会をつくるための力を身につける教育」と説明しています。
つまり、平和教育は「知識」だけではなく、「考え方」や「態度」「話し合う力」「協力する力」なども含む、総合的な学びなんです。
学問としての平和教育
ところで、「平和教育って授業で習うような学問なの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
実は、「平和教育」は単独の伝統的な学問分野ではありません。
けれど、平和学や教育学と深く関わる、実践的かつ学際的(いろいろな分野の知識や考え方を組み合わせた)研究分野とされています。
つまり、教育・心理・国際関係・社会学・政治・哲学など、さまざまな学問の視点から研究されていて、「どうすれば人と人とが平和に生きられるか?」という問いに、多角的にアプローチしているのです。
その意味で、平和教育は“教室の中だけ”で完結する学びではなく、現実社会の問題と向き合いながら、平和な社会を実現する力を育てる重要な分野なんですね。
「平和学習」との違いは?
「平和教育」と似た言葉に「平和学習」というものがあります。
よく学校で原爆や戦争のことを学ぶ授業を「平和学習」と呼ぶことがありますね。
「平和学習」は「平和教育」の一部と考えることができます。
「平和学習」は主に特定のテーマ(たとえば戦争体験や人権問題)について学ぶ活動に使われることが多く、授業や行事などで行われます。
一方、「平和教育」はもっと広い考え方で、「日常の生活すべてに平和の視点を取り入れていこう」という考え方なんです。
だからこそ「平和教育」は、道徳や社会の授業だけでなく、他の教科の授業や部活動、学校行事など、さまざまな場面に関わってきます。
日本の平和教育:戦争体験を伝える
日本の学校では、「平和で民主的な社会をつくる力」を育てることが教育の大きな目的のひとつとされています。そのために、戦争の歴史や人権、国際理解などを学ぶ「平和教育」が行われています。
たとえば、道徳や社会科の授業で戦争や差別について学んだり、広島や長崎への修学旅行で被爆体験を学ぶことがよくあります。ただし、こうした平和教育は学校ごとに差があり、毎年の特別行事で終わってしまうことも多いのが現状です。
まとめ:私たちにできる「平和教育」
平和教育は、世界のどこかで起きている問題だけではなく、私たち自身の暮らしや人間関係と深くつながっています。
たとえば、友達とけんかをしたときに「どう話し合えばよかったんだろう」と考えること。
ニュースで戦争や差別の問題を見たときに、「自分にできることは何だろう」と考えること。
違う考えを持つ人と出会ったときに、「相手の話をちゃんと聞こう」と思うこと。
それも、立派な平和教育なんです。
主な参考文献
- Biswas, S. (2020). Peace education: A brief overview. ResearchGate.
- UNESCO. (2015). Education for peace: Planning for curriculum reform.
- Hague Appeal for Peace. (2005). Conflict resolution education: A guide to implementing programs in schools, youth-serving organizations, and community and juvenile justice settings.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). (2020). The new course of study and its aims in Japan.
- Orihara, T. (2009). Peace education in Japan’s schools: A view from the front lines. The Asia-Pacific Journal: Japan Focus.