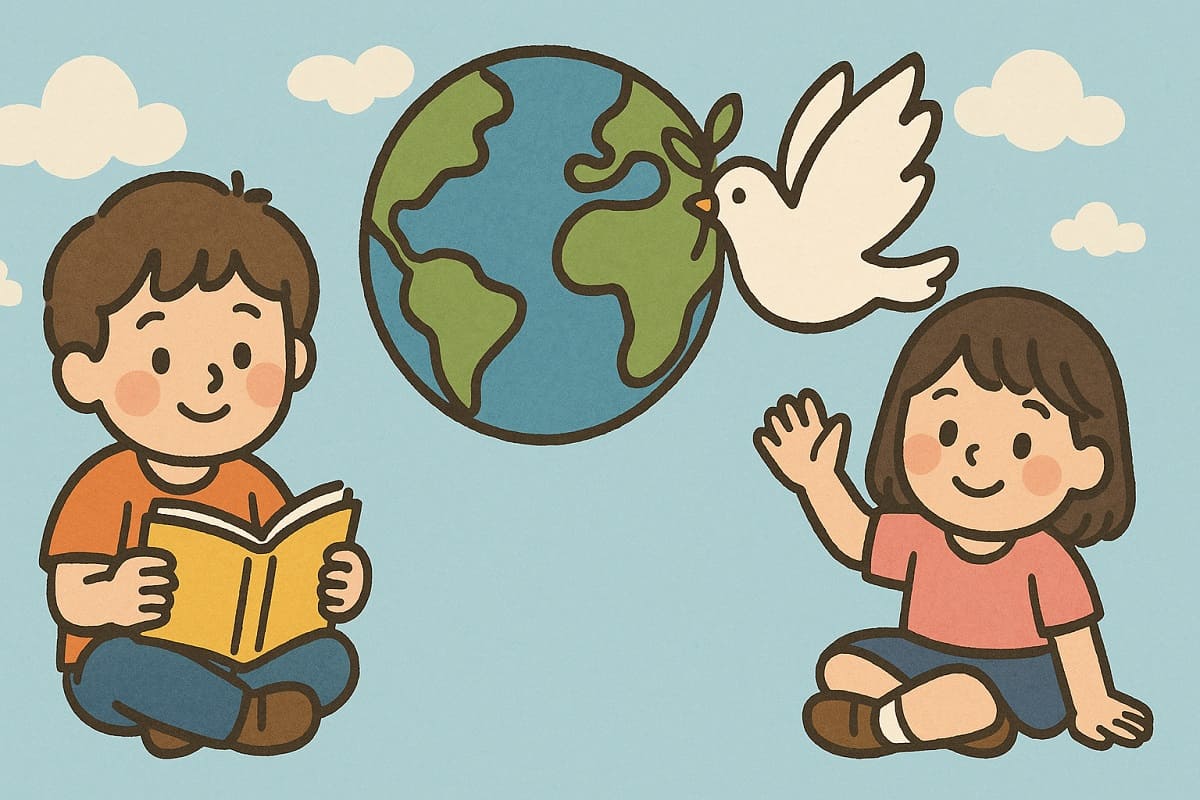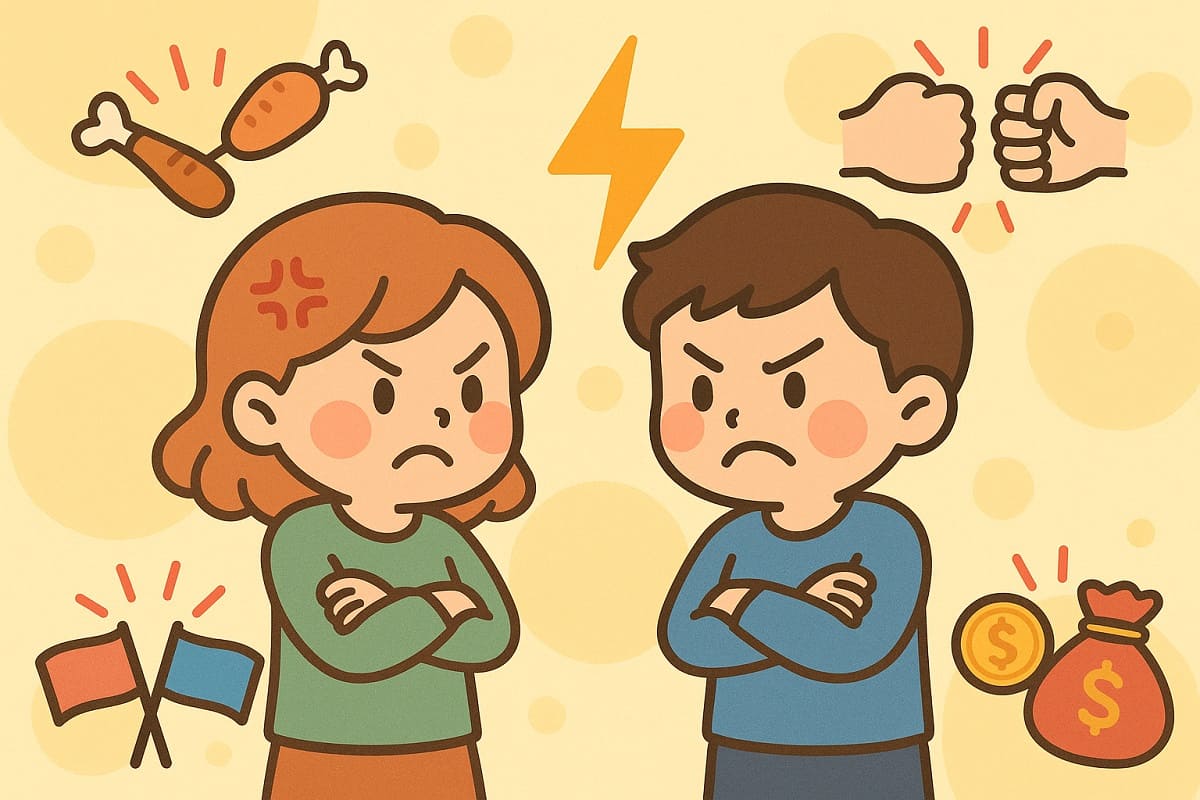Peace Techってなに? テクノロジーを平和に活用しよう

みなさんは、「テクノロジー」と聞いて何を思い浮かべますか? スマホ、AI、ロボット、ドローン…。今では生活に欠かせないものばかりですよね。
これらのテクノロジーを「世界の平和」に役立てる方法があるんです。それが「PeaceTech(ピーステック)」と呼ばれる考え方です。
PeaceTechって何?
「PeaceTech(ピーステック)」とは、簡単に言うとテクノロジーを使って戦争や争いを防いだり、平和をつくったりすることです。
たとえばこんなことができます:
- 衛星画像やAIを使って、戦争が起こりそうな地域を予測
- SNSを使って平和なメッセージを広める
- ブロックチェーン技術で、難民への食料支援を安全に管理する
つまり、テクノロジーを「争いを広げる道具」ではなく、「争いをなくすための道具」として使おうという考え方です。
PeaceTechのはじまりと広がり
ピーステックの動きは2008年にアメリカで始まりました。米国平和研究所(USIP)が「PeaceTechチーム」をつくり、2014年には「PeaceTech Lab」という専門の団体もできました。
そこから、スタンフォード大学やヨーロッパの大学、NGOなどが次々に関わるようになり、今では国連や各国政府も注目する分野になっています。
どんな技術が使われているの?
PeaceTechで使われている技術は、思っているよりずっと幅広いんです。
● 通信やSNS
ラジオやSMS、LINEやXのようなSNSで、争いを防ぐ情報を発信したり、対話のきっかけを作ったりします。
● AIとビッグデータ
AIがSNSの投稿を分析して、暴力的な発言や紛争の兆しを早く見つけることができます。
● ドローンと衛星
ドローンで避難所の様子を調べたり、衛星で停戦ラインを見張ったりします。
● ブロックチェーン
安全に支援物資やお金のやりとりをするために使われています。ヨルダンでは、難民が虹彩スキャンで食料を受け取るシステムも運用中です。
● VR(仮想現実)
仮想空間で平和教育の体験ができるようなシミュレーターもあります。
世界のPeaceTech事例
ここでは、いくつかの実例を紹介します。
【1】争いを防ぐ:早期警戒と情報発信の工夫
■ Ushahidi(ウシャヒディ)/ケニア
ケニアでは、選挙のたびに暴力が起こることが問題でした。そこで市民団体が作ったのが「ウシャヒディ」というウェブサービス。人々がスマホやネットを通じて暴力や不正を報告でき、その情報が地図に表示される仕組みです。
これにより、「今どこで危険があるのか」がリアルタイムで見えるようになり、暴力の拡大を防ぐことに成功しました。
■ Sisi ni Amani(シシ・ニ・アマニ)
同じくケニアで、争いのときに広まるウワサやデマを止めるために、SMS(携帯のショートメッセージ)で「平和のメッセージ」をたくさんの人に送りました。
SNSやテレビが見られない人にも伝えることができ、パニックを防ぎました。
■ AIとSNSのモニタリング
最近はAIを使ってXやFacebookの投稿を分析し、「危ない発言」や「ヘイトスピーチ(差別や暴力をあおる発言)」を自動で見つけて警告するプロジェクトも増えています。
まるで“平和のセンサー”のように、人の怒りが爆発する前に察知してくれる仕組みです。
【2】争いの後を支える:話し合いと見える化
■ 停戦後の監視にドローンや衛星
紛争が終わったあとの「停戦が守られているか」を見守るのに、ドローンや衛星画像が使われています。人が近づけない危険な地域でも、空から監視できます。
住民を守る「目」として国連のPKO(平和維持活動)でも導入されています。
■ SNSやセンサーで暴力の記録
たとえば、ある地域で誰かが攻撃されている動画が投稿されたとします。そのデータを保存し、あとで証拠として使えるようにする仕組みがあります。
【3】支援の最前線:人道テックの進化
■ WFP「Building Blocks」/ブロックチェーン
ヨルダンの難民キャンプでは、WFP(国連世界食糧計画)がブロックチェーン技術を使って、難民一人ひとりに「食料支援の記録」を管理。現地の商店で虹彩(目の模様)スキャンをして、現金の代わりに食料を受け取る仕組みです。
これにより、不正やムダがなくなり、支援の効率も大幅アップしました。
■ ドローンで薬を届ける
山道や危険地帯では、医薬品や食料を届けるのもひと苦労。そんなときはドローンが大活躍。GPSで自動運転し、最短ルートで物資を運んでくれます。
■ 遠隔教育・遠隔医療(テレメディスン)
インターネットを使って、難民キャンプにいる子どもたちが学校の授業を受けたり、お医者さんに相談したりできる取り組みも進んでいます。
PeaceTechの課題
テクノロジーには明るい面もありますが、注意が必要な点もあります。
- 悪用されるリスク:SNSがフェイクニュースやヘイトスピーチに使われることも。
- 格差の問題:スマホやネットが使えない人が取り残される可能性も。
- プライバシー:監視のために個人情報が大量に集められ、悪用される危険もあります。
こうした問題にどう向き合うかも、PeaceTechを進めるうえで大事なテーマです。
まとめ
PeaceTechは、まだ始まったばかりの新しい取り組みです。でも、世界中の人が協力してテクノロジーを平和のために使うことができれば、戦争や暴力のない未来に一歩近づくかもしれません。
「テクノロジーって、平和にも使えるんだ!」
そんな気づきから、未来を変える一歩が始まるのかもしれません。
主な参考文献
- PeaceTech Lab. (n.d.). PeaceTech: What Is It?. Retrieved from
- The GovLab. (n.d.). What is PeaceTech?.
- Toda Peace Institute. (n.d.). 25 Spheres of Digital Peacebuilding and PeaceTech.
- Forbes Japan. (2021). テクノロジーが世界を救う? PeaceTechの可能性.
- United Nations. (2020). Impact of Digital Technologies.