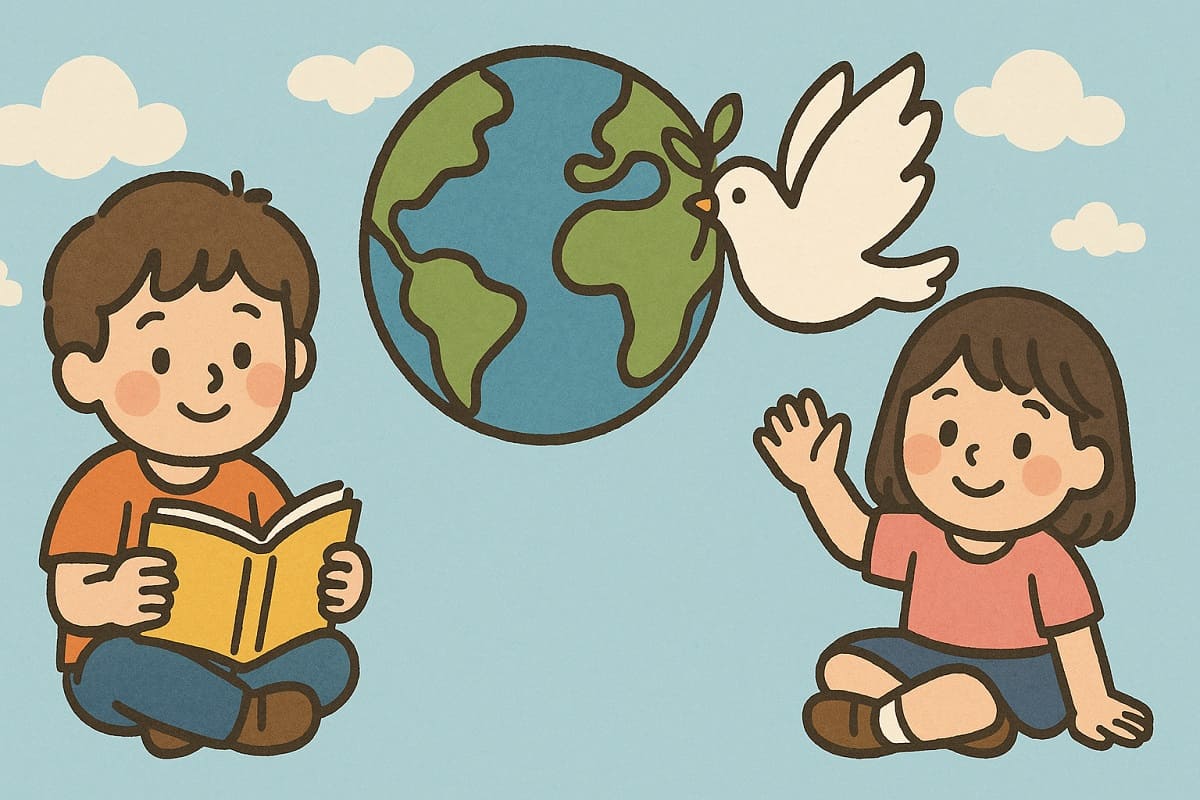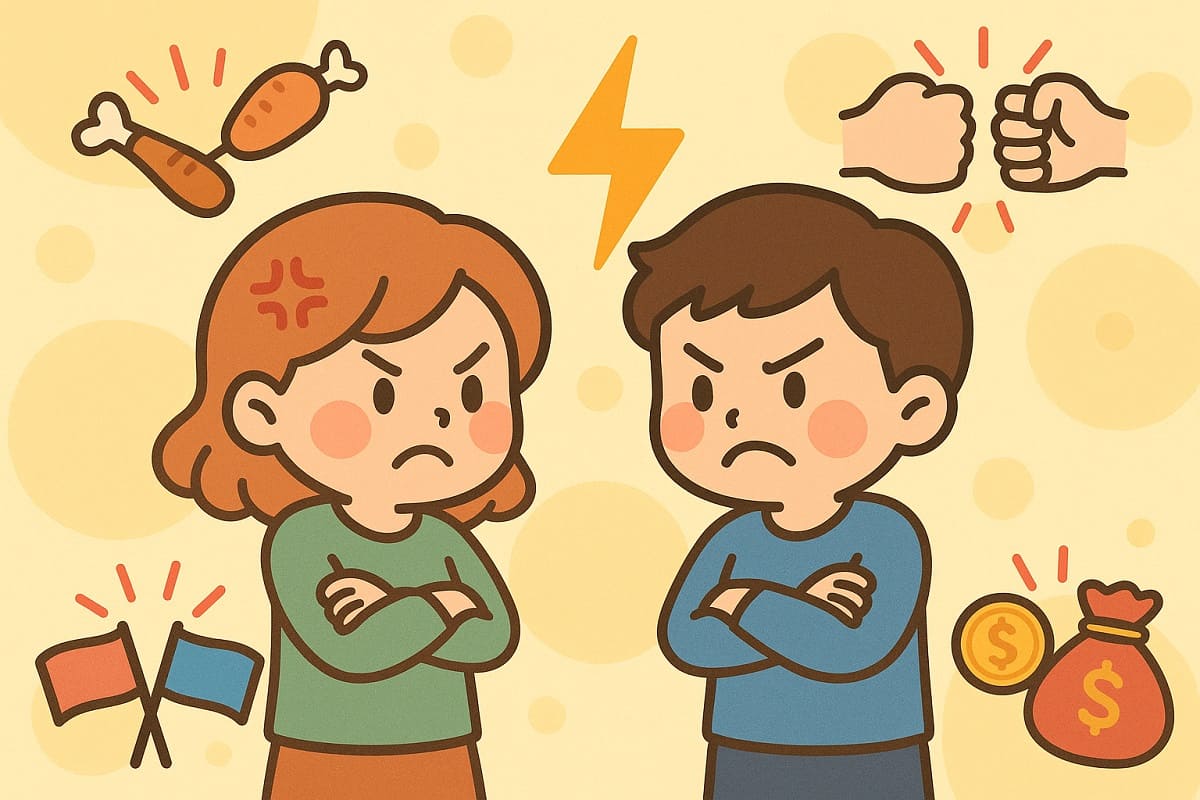パワハラはなぜ起こるの? パワハラが起きる日本の職場に特有の原因を知ろう

「パワハラ」という言葉を聞いたことがありますか?
これは「パワーハラスメント」の略で、職場での立場の強い人が、立場の弱い人に対して行う嫌がらせのことを指します。たとえば、上司が部下に怒鳴ったり、人前で恥をかかせたり、無理な仕事を押しつけたりすることです。
最近はニュースやSNSでも「パワハラ」という言葉を目にする機会が増えてきました。でも、どうしてパワハラは起こるのでしょうか?特に、日本の職場ではなぜパワハラが起こりやすいのでしょうか?
今回は、日本の社会や職場の特徴から、パワハラが起きやすくなる「しくみ」についてわかりやすく解説します。
パワハラってどんなもの?
まずは、パワハラの定義を確認しておきましょう。
厚生労働省によると、パワハラは以下の3つの条件をすべて満たすとされます。
- 職場での優越的な関係(上司・先輩など)を背景にした言動
- 業務上必要な範囲を超えた行動(つまり、やりすぎ)
- 働く人の心や体に悪影響を与えるもの
たとえば、「仕事のミスを何度も大声で怒鳴る」「私生活のことまでバカにする」「誰もいない部署に一人だけ異動させる」などがこれにあたります。
こうしたパワハラは、被害を受けた人の心を深く傷つけ、うつ病などのメンタル不調や退職、自殺につながってしまうこともあります。
では、なぜこんなひどいことが職場で起きてしまうのでしょうか?
日本の職場でパワハラが起こりやすい理由
1. 年功序列と上下関係の強さ
日本では長い間、「年齢や勤続年数が上の人がえらい」という価値観が大切にされてきました。これを「年功序列」といいます。
この制度では、年上や上司の言うことには逆らってはいけないという空気が職場にあります。たとえ上司の言動がおかしくても、「黙って従うのが当たり前」と思われてしまうのです。
このように、強い上下関係があると、上の立場の人が自分の力を乱用して、部下に理不尽な命令を出したり、怒鳴ったりしても、まわりが注意できなくなってしまいます。
2. 「空気を読む」文化と同調圧力
日本では「みんなと同じであること」が重視される傾向があります。これは「同調圧力(どうちょうあつりょく)」と呼ばれています。
「上司に誘われた飲み会は断ってはいけない」「残業している人がいるのに、自分だけ先に帰るのは悪い」など、本当はやりたくなくても空気を読んで我慢してしまうことってありますよね。
この「空気を読む」文化が強いと、「あの上司の言動はおかしい」と感じても、だれもそれを指摘できなくなってしまいます。結果として、パワハラを見過ごしてしまう空気が生まれてしまうのです。
3. 職務内容がはっきりしていない
日本の多くの会社では、「あなたの仕事はこれです」という職務内容(具体的な仕事の内容)がはっきり決まっていません。
そのため、上司が「これもやって」「あれも手伝って」と無理に仕事を押しつけても、部下は「自分の仕事じゃありません」と言いづらいのです。
このように、どこまでが正当な「仕事の指示」で、どこからが「やりすぎのパワハラ」なのか、判断があいまいになりやすいのです。
4. 転職しにくい社会
日本では、「一度入った会社でずっと働くのが理想」という考え方がいまも残っています。
そのため、たとえ職場でパワハラが起きても、「この会社を辞めたら再就職が難しいかもしれない」「あと何年か我慢すれば…」と思ってしまい、なかなか声を上げることができません。
逃げ場がない状態が続くことで、心のダメージがどんどん大きくなってしまうのです。
海外と比べてどうなの?
海外、特に欧米の企業では、職務内容がしっかり決まっていたり、働き手の権利が法律で守られていたりします。
たとえばフランスでは、2002年から「モラルハラスメント(精神的ないじめ)」を法律で禁止していますし、職場で理不尽なことがあれば、すぐに訴えたり、転職したりする文化もあります。
それに比べて、日本ではパワハラに対する法律の整備が遅れ、相談する場所が少なかったり、声を上げづらい文化が根強く残っていたのです。
最近では、ようやく2020年から企業にパワハラ防止措置が義務化され、相談窓口を作ったり、研修を行ったりする企業が増えてきました。
でも、制度ができても、それを活用しやすい空気を作っていかないと、実際には何も変わらないままになってしまいます。
パワハラをなくすために大事なこと
では、どうすればパワハラをなくしていけるのでしょうか?
ポイントは、「会社」「社会」「一人ひとり」が、それぞれできることをしっかり考えることです。
● 会社ができること
- パワハラを許さない方針をはっきりと打ち出す
- 相談窓口を設置して、安心して声を上げられる環境をつくる
- 上司・管理職向けに、適切な指導方法を学ぶ研修を行う
● 社会ができること
- 法律や制度をよりわかりやすく、使いやすく整える
- 学校などで「人権」「働く人の権利」について学ぶ機会を増やす
- メディアなどでハラスメントの問題をもっと取り上げる
● 私たち一人ひとりができること
- 「これはおかしい」と思ったら、信頼できる人や専門の窓口に相談する
- 周りの人が困っているときに、勇気を持ってサポートする
- 「指導すること」と「相手を傷つけること」は違う、と意識する
おわりに
パワハラは、たったひとりの悪意から始まるのではなく、社会の仕組みや職場の文化が原因となって起きることが多いものです。
でも、ひとつひとつの仕組みや考え方を変えていくことで、少しずつでもパワハラを減らしていくことは可能です。
「誰かを傷つける空気」に気づき、「みんなが安心して働ける場所」をつくるために、私たちも小さな行動から始めてみませんか?
主な参考文献
- 厚生労働省. (2024). 職場のハラスメントに関する実態調査報告書(令和5年度).
- 厚生労働省雇用環境・均等局. (2019). 改正労働施策総合推進法ガイド.
- 連合総合生活開発研究所. (2010). ハラスメントと職場風土—パワハラのない職場づくりに向けて. DIO No.255.
- JILPT. (2022). 諸外国におけるハラスメントに係る法制. 研究報告書 No.216.
- リクルートワークス研究所. (2020). 職場のハラスメントを解析する(JPSED分析報告書2020).