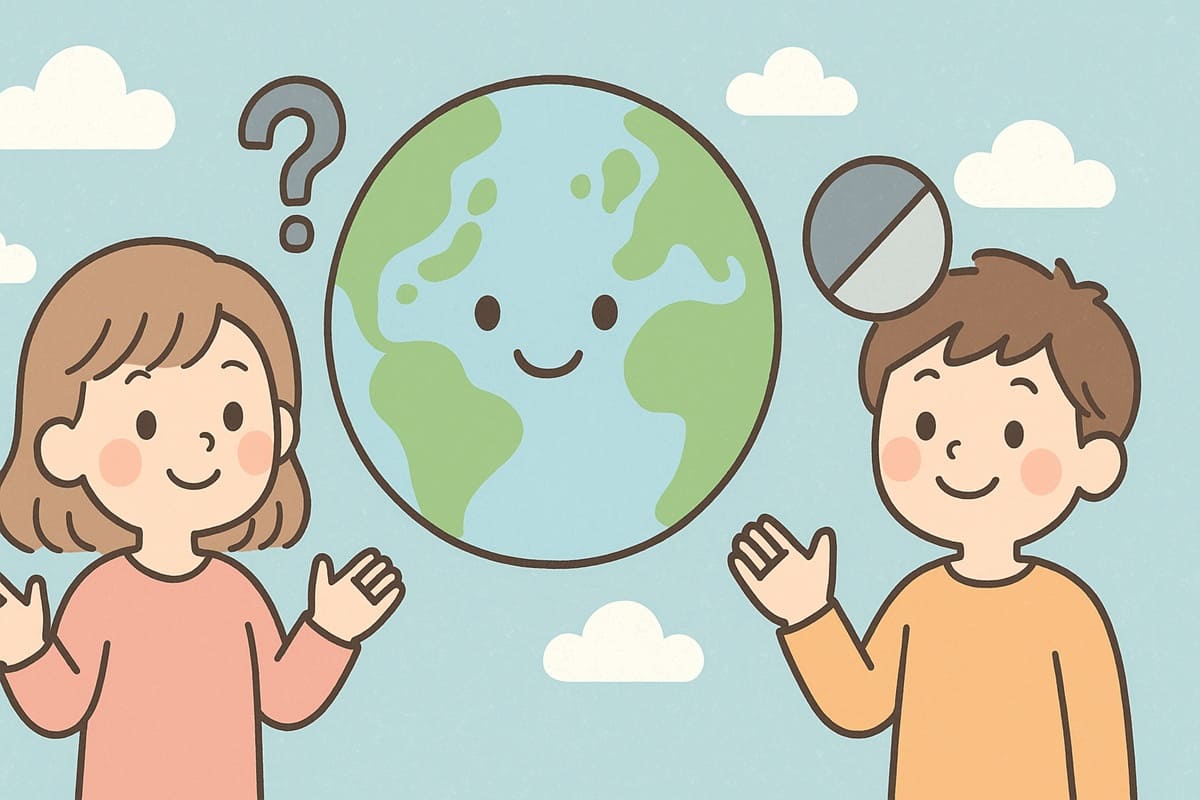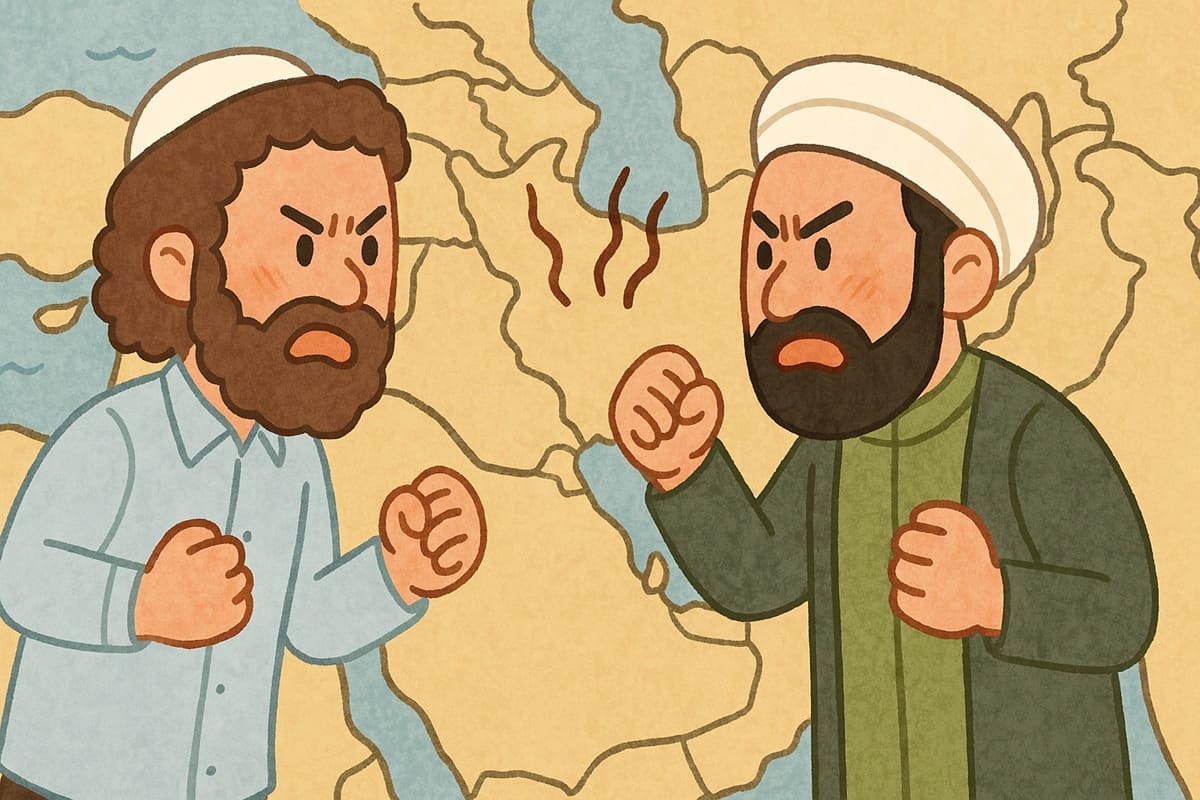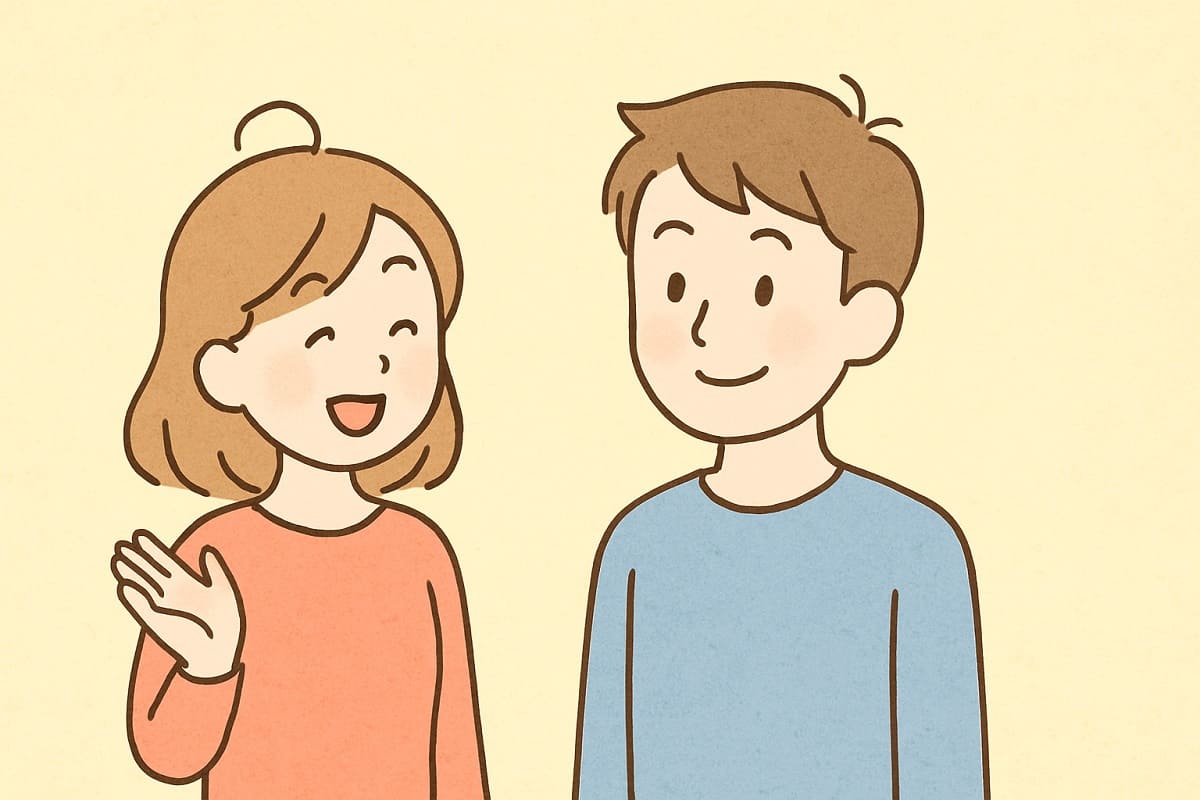どうしたらお互いに協力できるの? 「囚人のジレンマ」を理解しよう

ニュースで「戦争」や「軍拡競争」といった言葉を聞くと、「どうして人間はもっと協力できないんだろう?」と思ったことはありませんか?
仲良くすればいいのに、どうして争ってしまうのか。それには、「囚人のジレンマ」という考え方が関係しています。
今回は、ゲーム理論という分野から生まれた「囚人のジレンマ」について、わかりやすく説明しながら、「どうすれば協力し合えるのか」を一緒に考えてみましょう。
囚人のジレンマってなに?
「囚人のジレンマ」は、ゲーム理論という数学的な考え方から生まれた、ちょっとした“思考実験”です。
ある日、2人の容疑者が一緒に犯罪をしたとして逮捕されたとします。でも、証拠がはっきりしないので、警察はそれぞれ別々に尋問することにします。
警察はこう言います:
- 「君が相手のことをチクって自白すれば、君は無罪にしてあげる。でも相手が君をチクったら、君は5年の刑だよ。」
- 「もし2人とも黙っていれば、軽い罪で1年の刑だけで済むよ。」
- 「でも、2人ともチクったら、証拠がそろうから、それぞれ3年の刑にするからね。」
つまり、それぞれに次のような選択肢があります。
| 相手が黙る | 相手が自白する | |
|---|---|---|
| 自分が黙る | 1年ずつ | 自分5年、相手0年 |
| 自分が自白する | 自分0年、相手5年 | 3年ずつ |
自分だけが「自白」すれば無罪で済む可能性がある。でも、お互いに「自白」を選ぶと、両方とも損をしてしまうんです。
もし2人が信じ合って黙っていれば、軽い刑ですむのに、“自分だけ助かりたい”という思いが裏切りを生み、結局は両方にとって悪い結果になる…。
これが「囚人のジレンマ」の構造です。
この話が平和に関係あるの?
「囚人のジレンマ」はただの空想の話ではありません。実は、国と国の関係、戦争、軍拡競争、環境問題などにも関係しているんです。
たとえば、A国とB国という2つの国があるとします。お互いに「軍備を増やすか」「軍備を増やさないか」の選択ができます。
- もし2国とも軍備を増やさなければ、安全でお金もかからず平和です。
- でも、「相手が攻めてきたら危ない」と思うと、先に武器を増やしたくなります。
- その結果、両方が軍拡してしまい、「お互い疑い合ってどんどん武器を増やす」状態に陥ってしまうんです。
これが、現実の世界でも見られる「囚人のジレンマ」的な状況です。お互いのことを信用できないと、協力するよりも“先に動いた方が勝ち”という考えに支配されてしまうんですね。
協力するにはどうしたらいいの?
それじゃあ、どうすれば私たちは「協力」を選べるようになるのでしょうか?
実は、いくつかのヒントがあります。
1. 長く付き合う前提で考える
「囚人のジレンマ」は1回だけの勝負では裏切りが得になることが多いですが、何度も繰り返す勝負になると、協力の方が得になることがあります。
なぜなら、相手に裏切られたら、次回はこちらも裏切ろうという「仕返し」をするようになるし、逆に相手が協力してくれたら、こちらも協力することで信頼のサイクルが生まれるからです。
このような考え方を「繰り返しゲーム」と言います。
実際に、アメリカの政治学者ロバート・アクセルロッドは、いろいろな戦略を試して競わせたコンピュータ大会を行い、「最初は協力し、次は相手の行動をマネする」戦略(TFT=Tit for Tat)が一番うまくいったという結果を得ました。
つまり、最初は信じて協力しようとすること。そして裏切られたらそのときだけ仕返しするなどの対応をして、次回からはまたチャンスをあげること。
この姿勢が、長期的に見るとお互いにとって一番いい結果を生み出すのです。
2. ルールを作る・信頼を見える化する
現実の世界では、「約束を守る」「相手の行動が見える」「ルールを破ったときの罰がある」といった仕組みを作ることで、協力がしやすくなります。
たとえば、国際条約や環境協定は、協力を強制するルールです。
また、本当にルールを守っているかを監視する監視機関や査察チームを作ることで、「相手が本当に協力しているかどうか」がわかるようになります。
これは、言い換えれば「ゲームのルールを変えること」で、協力する方が得になるように仕組みを作り直すという考え方です。
3. おたがいの立場を理解しようとする
最後に、もっとも基本的で大事なことは、相手の立場を理解しようとする姿勢です。
「どうしてあの国はああいう行動を取るのか?」「本当に信じられない相手なのか?」「もしかしてこちらの行動が不信を生んでるのかも…?」
そうやって“相手の目線”で物事を考えてみることが、協力への第一歩になるかもしれません。
囚人のジレンマから学べること
「囚人のジレンマ」は、単なる数学的なパズルではなく、人間社会や国際関係の中で実際に起こっていることをうまく説明してくれる考え方です。
・相手を信じるのは簡単じゃない。
・でも、信じなければずっと争いが続く。
・だからこそ、どうやって信じ合えるか、協力しあえるかを考えることが大切なんです。
平和とは、誰かに「与えられる」ものではありません。
お互いに努力して築くものです。
そのためにも、まずは「囚人のジレンマ」という“協力のむずかしさ”を理解して、どうすれば乗り越えられるのかを一緒に考えていきましょう。