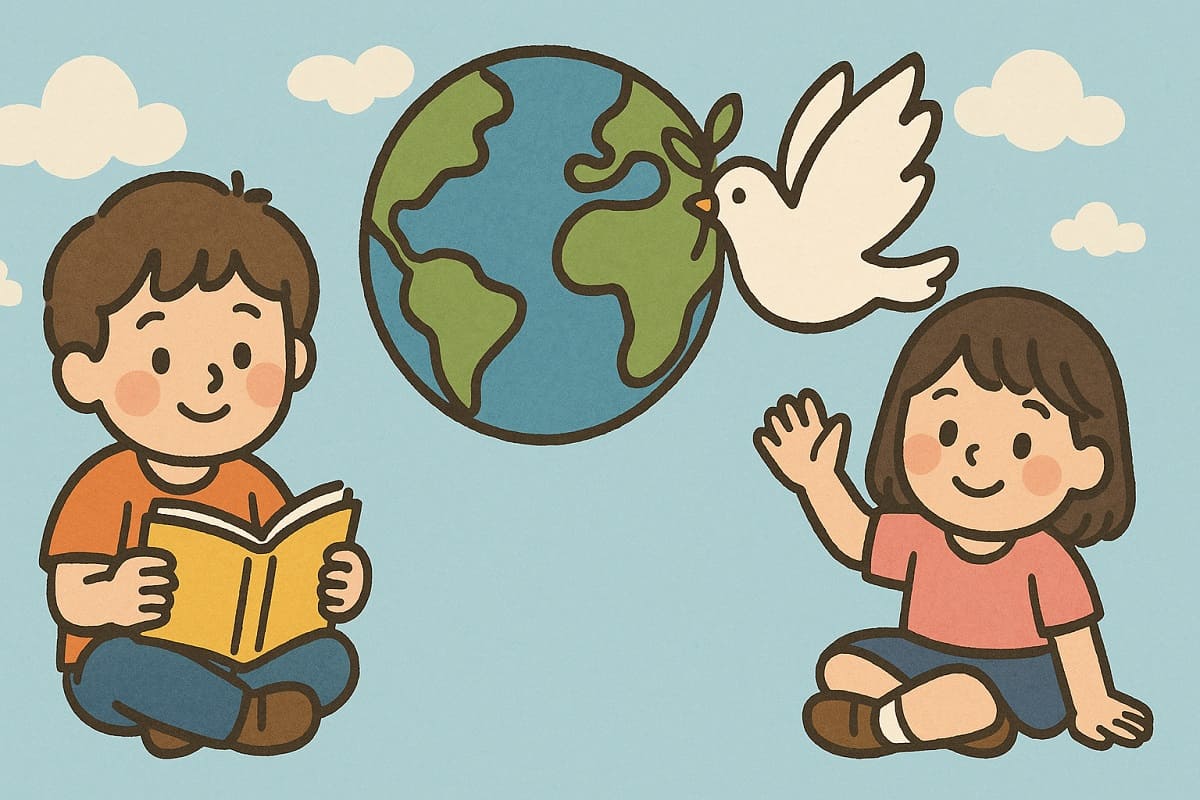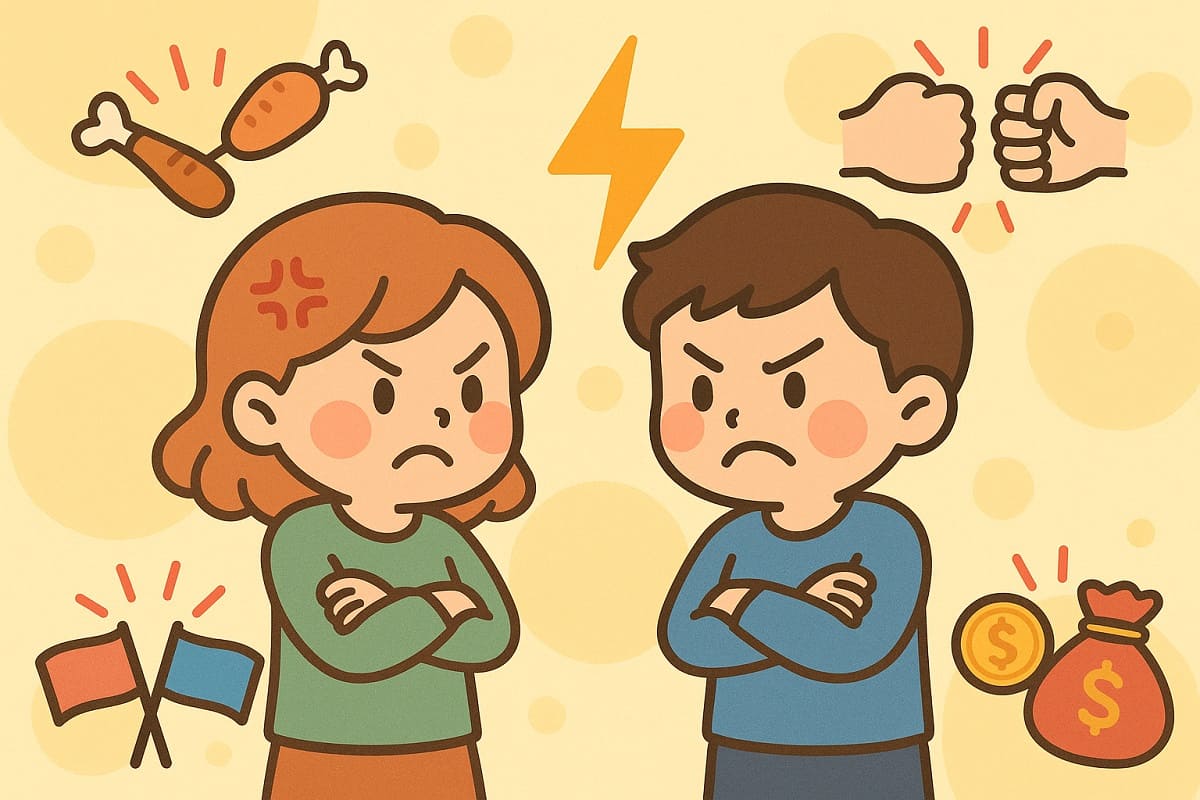戦争と音楽にはどんな関係があるの?

「戦争」と「音楽」。この二つを聞いて、どんなイメージが思い浮かびますか?
音楽といえば、ふつうは楽しい気分になれるもの、心を落ち着かせるもの、友だちと盛り上がれるもの……そんな印象があるかもしれません。でも、実は音楽は、昔から戦争と深く関わってきました。
今回は、「戦争と音楽にはどんな関係があるのか?」について、歴史や心理学の視点からくわしく見ていきましょう。
昔から戦場には音楽があった
戦争と音楽の関係は、じつはとても古くから存在します。たとえば、19世紀のナポレオン戦争(1800年前後)では、兵士たちが戦場で太鼓やラッパを鳴らしていました。これは、ただの演出ではありません。音楽には「戦うぞ!」という気持ちを高めたり、行進のタイミングを合わせたり、命令を伝える役目があったのです。
戦争が進むにつれ、音楽はどんどん重要になっていきます。20世紀に入ると、第一次世界大戦(1914〜1918年)では、兵士たちが塹壕(ざんごう)で歌を歌ったり、携帯型のレコードプレイヤーで音楽を聴いたりして、不安や孤独をまぎらわしていたそうです。
また、アメリカでは「Over There(向こうの戦場へ)」という愛国歌が大ヒットし、若者の戦意を高めるプロパガンダ(宣伝)に使われました。こうした戦争と音楽の関係は、第二次世界大戦(1939〜1945年)でもさらに広がり、ラジオや映画を通じて、音楽は国民全体の「やる気スイッチ」のような役割を果たしていたのです。
音楽で「やる気」を出す?戦意を高める曲とは
戦争のときによく使われるのが「行進曲(マーチ)」や「軍歌」と呼ばれる曲です。こうした音楽には、いくつかの共通した特徴があります。
- テンポが速く、リズムがはっきりしている
- メロディーが覚えやすい
- 「勝利」「祖国」「勇気」などの言葉がよく出てくる
- 合唱しやすく、みんなで一緒に歌える
たとえば、第一次世界大戦で人気だった「Pack Up Your Troubles(悩みなんてカバンにつめて)」は、明るく楽しいメロディーで、「大丈夫、笑っていこう!」というポジティブなメッセージがこめられています。
こうした曲は、兵士たちが恐怖に負けないように勇気をふるい立たせるために、とても効果的でした。音楽のリズムに合わせて行進したり、仲間と一緒に歌ったりすることで、「自分は一人じゃない」という安心感が生まれ、チームとしての団結力も高まります。
このように、音楽は戦場だけでなく、戦争を続ける社会全体の「やる気」や「士気(しき)」を支える力になっていたのです。
音楽で「戦争はダメだ」と伝える人たちも
でも、音楽が戦争を応援するためにだけ使われていたわけではありません。むしろ逆に、「戦争はまちがっている」「平和を大切にしよう」というメッセージを音楽で伝えようとした人たちもたくさんいます。
たとえば、1915年にアメリカで発表された「I Didn’t Raise My Boy to Be a Soldier(息子を兵士に育てたんじゃない)」という曲は、「他の誰かを殺すために、息子を育てたわけじゃない」と母親の視点から戦争を批判する歌でした。
特に、1960年代のベトナム戦争のころには、反戦の音楽が大きなブームになりました。ボブ・ディランやジョーン・バエズといったフォーク歌手たちが、ギター1本で平和を訴える歌を歌い、多くの若者たちが共感しました。
たとえば、ボブ・ディランの「風に吹かれて」は、「答えは風の中にある」と繰り返すことで、社会の不正や戦争への疑問を詩的に表現した名曲です。
こうした「反戦ソング」は、ただ聴くだけでなく、集会やデモでみんなで歌うことで、平和を願う人たちの一体感や連帯感を生み出す力になっていきました。
心を動かす音楽の力―心理学から見た「戦争と音楽」
では、なぜ音楽には、こんなにも人の心を動かす力があるのでしょうか?
心理学の研究では、音楽には人間の感情を強くゆさぶる力があることがわかっています。たとえば、明るい音楽を聴くと気分が明るくなり、暗い音楽を聴くと気持ちが沈む……というのは、みなさんも経験があるのではないでしょうか?
戦争中には、この「感情のスイッチ」をうまく使って、兵士や国民の気持ちをコントロールしようとする動きがありました。
たとえば、行進曲を使えば、兵士たちがリズムに合わせて歩きやすくなるだけでなく、「前へ進め!」という気持ちが自然と湧いてくるようになります。これは、音楽の「テンポ」や「反復リズム」が脳に作用して、やる気や高揚感を生み出すからだと考えられています。
また、戦争が終わったあと、音楽は心の傷をいやすためにも使われました。つらい体験をした兵士たちが、自分の気持ちを音楽で表現することで、少しずつ心が軽くなっていくのです。最近では「音楽療法」といって、PTSD(心のトラウマ)を持つ人への治療に音楽を使う方法も研究されています。
音楽は、戦争の道具?それとも平和の願い?
ここまで見てきたように、音楽は戦争の中でさまざまな形で使われてきました。
- 兵士の士気を高める
- 国民の心を一つにする
- 戦争に反対する気持ちを広める
- 戦争で傷ついた心をいやす
音楽はときに人を戦いに向かわせ、ときに平和を願う声を届けます。
つまり、音楽そのものが「良い」か「悪い」かではなく、それをどう使うか、どんな目的のために使うかが大切なのです。
私たちが音楽を楽しむとき、その背後にある「メッセージ」や「歴史」にも目を向けてみると、音楽の持つ力をもっと深く理解できるかもしれません。
そして、これからの時代、音楽が「争い」ではなく「平和」のために使われていくことを、心から願いたいですね。
参考文献
- O’Keeffe, E. (2023). Bold as brass: Napoleonic Wars veterans and the origins of Britain’s brass band tradition. University of Cambridge.
- Okada, A. (2014). Music. In 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War.
- HistoryNet Staff. (2006). The Music of War. HistoryNet.
- Pieslak, J. (2009). Sound Targets: American Soldiers and Music in the Iraq War. Indiana University Press.
- Deutsche Welle. (2025). Vietnam War: How protest music fueled a movement.