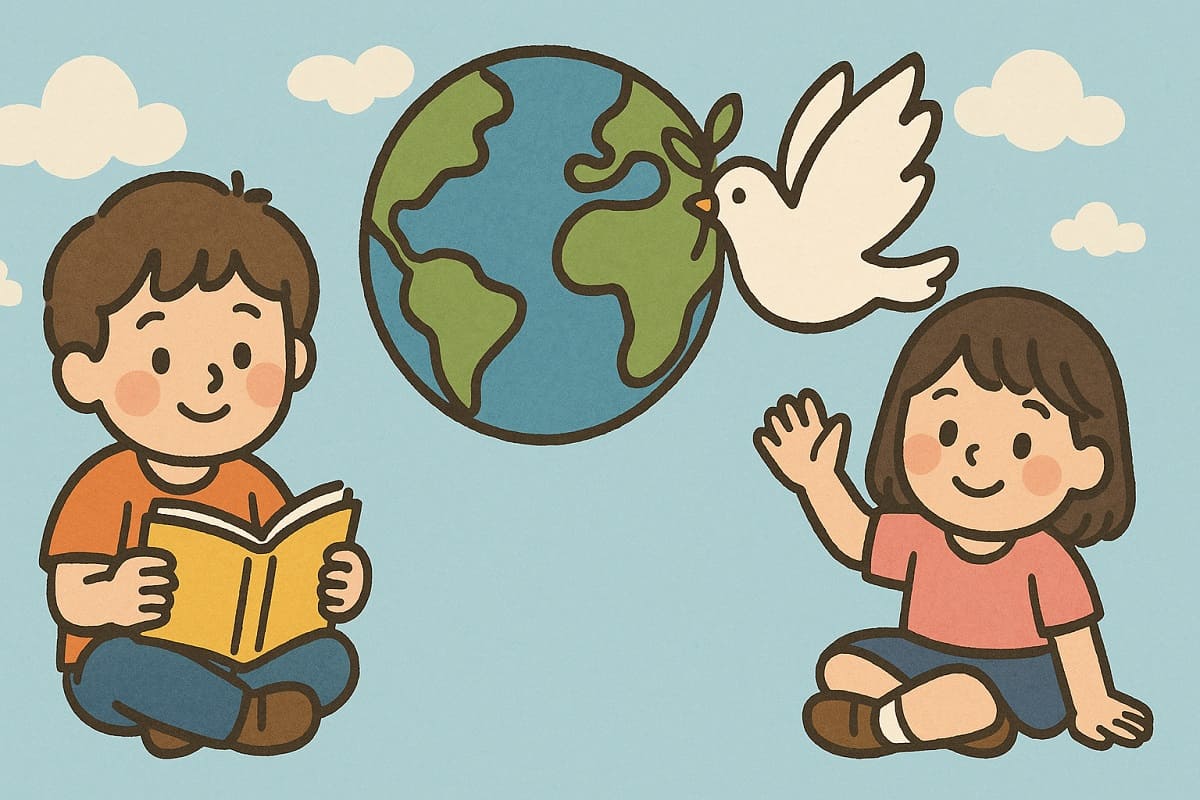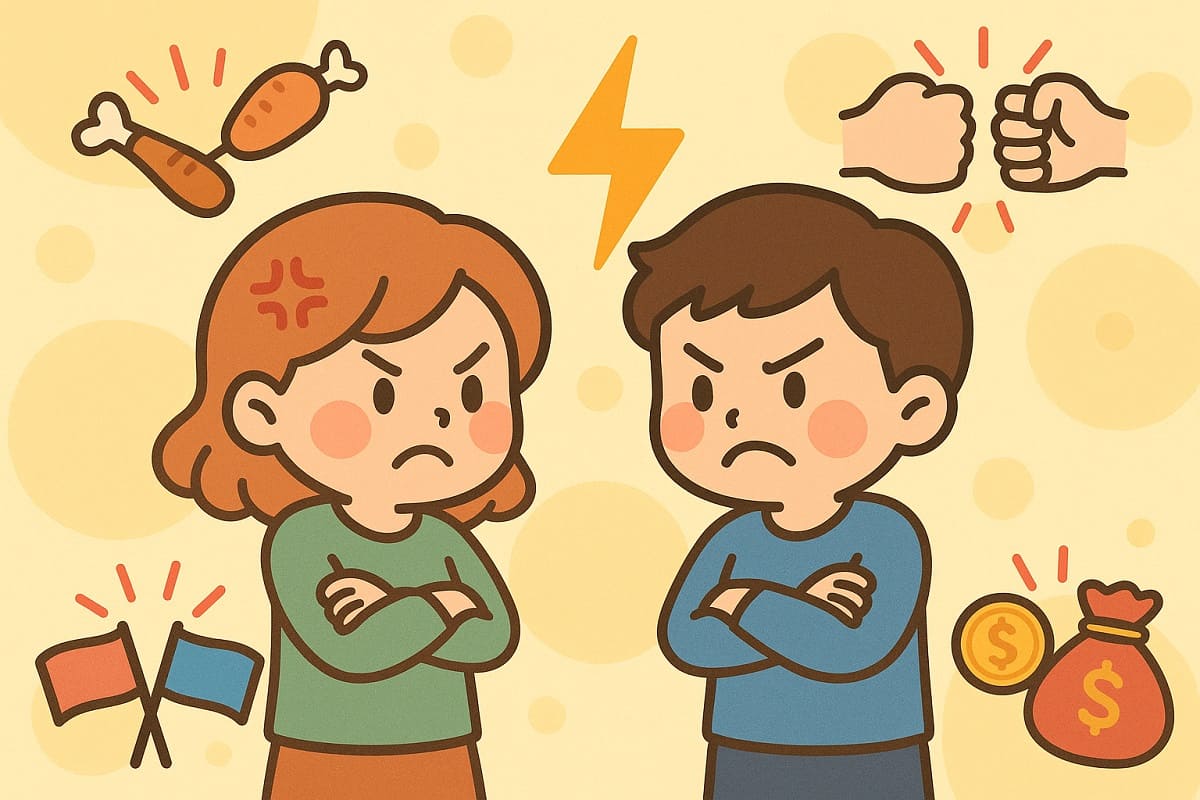戦場では誰が戦っているの? 徴兵制と志願制の違いを知ろう

「戦争に行く人って、どうやって決まるの?」
「今の時代に、戦争に行くなんてことあるの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
私たちが暮らすこの世界では、今もなお戦争や武力衝突が続いている地域があります。そしてそこには、実際に戦っている“誰か”がいます。でもその「誰か」は、決して特別な人ではなく、私たちと同じ普通の若者であることがほとんどです。
今回は、「戦場では誰が戦っているのか?」という問いに向き合うために、「徴兵制」と「志願制」という2つの制度の違いや、それぞれの制度がどんな人を戦場に送り出しているのかについて、わかりやすく説明します。
徴兵制と志願制ってなにが違うの?
まず、戦争で兵士になる仕組みには大きく2つあります。
● 徴兵制(ちょうへいせい)
これは国が法律で「一定の年齢の国民は必ず軍隊に行かなければならない」と決める制度です。本人の意思とは関係なく、国が命令すれば軍隊に入らなければなりません。
たとえば、韓国ではすべての成人男性に約1年半〜2年間の兵役義務があります。これは北朝鮮との緊張が続いているため、国を守るためにたくさんの兵士が必要だからです。
また、イスラエルでは男女どちらにも兵役義務があります。これは中東という不安定な地域にあるイスラエルにとって、国民全員で国を守る必要があるという考えからきています。
● 志願制(しがんせい)
こちらは「軍隊に入りたい人だけが入る」制度です。日本やアメリカなどはこの志願制をとっています。つまり、戦争に行くかどうかは基本的には本人の意思で決まります。
一見、「志願制のほうが自由でフェアじゃない?」と思うかもしれません。でも、実はこの制度にも落とし穴があります。
本当に自由?志願制の“見えない強制力”
志願制の国では、表向きは「好きな人だけが軍隊に入る」ように見えます。でも実際は、「経済的に苦しいから」「大学の学費が払えないから」「生活のために給料が欲しいから」といった理由で入隊する若者がたくさんいます。
たとえばアメリカでは、軍に入ると学費を払ってもらえたり、医療や住宅のサポートを受けられる制度があります。そのため、お金に困っている家庭の子どもたちや、移民の若者が「軍に入れば将来の道がひらける」と思って入隊することが多いのです。
つまり、志願制であっても、実際には「経済的な理由」で戦場に行かざるを得ない人が多くいるのです。こうした現象は、「経済的徴兵」とも呼ばれています。
みんなが進んで戦場に行くわけじゃない
兵士=戦いたい人、というイメージを持っていませんか? でも、実際にはそうではありません。
たとえばアメリカ軍のエーレン・ワタダ中尉という人は、「この戦争は正しくない」と考え、イラク戦争への派遣命令を拒否しました。軍法会議にかけられることを覚悟してでも、自分の良心を貫こうとしたのです。
また、戦地に派遣された兵士のなかには、精神的な負担や恐怖から「もう戻りたくない」と考えて、脱走したり軍をやめたりする人もいます。イラク戦争では、何千人もの兵士が戦場から逃げ出したという報告もあります。
ロシアでは2022年のウクライナ侵攻以降、徴兵された若者の中に「戦いたくない」と感じる人が多数いました。前線に送られた兵士のなかには、訓練不足で士気が低く、武器を置いて逃げたり、自らウクライナ側に投降したりする人もいたと報道されています。
戦争は「正義のために勇敢に戦うもの」というイメージとは違い、実際には多くの若者たちが恐怖や葛藤の中で戦場に立たされているのです。
だれが戦って、だれが戦わないのか
徴兵制では、建前上「すべての人が平等に兵役を負う」ことになっていますが、実際には政治家や有名人の子どもが特別扱いされたり、体調不良などで免除されたりすることもあります。
志願制では、富裕層や教育を受けた人は軍に入らず、貧しい人やマイノリティ、移民などが軍に多くなる傾向があります。アメリカでは、軍隊の中に占めるヒスパニックや黒人、移民の割合が年々増えています。
「誰が戦うか?」という問いは、「誰が戦わずにすむのか?」という問いでもあります。
お金がある人、社会的に強い立場の人は、戦争を「自分とは関係ないこと」として生きていくことができます。その一方で、弱い立場の人が戦争の現場に送り込まれているのです。
まとめ:戦争の現場にいるのは、普通の若者たち
戦争を始めるのは政府や軍の上層部かもしれません。でも、実際に戦場に行って命をかけるのは、ほとんどが普通の市民――とくに若者です。
徴兵制でも志願制でも、社会の中でより弱い立場にいる人が戦場に向かう傾向があるという事実は、私たちが見落としてはならないポイントです。
戦争のニュースを見るとき、そこには「どこか遠くの誰か」ではなく、あなたと同じような人がいるかもしれない――そんな想像力を持つことが、平和を考える第一歩になるかもしれません。
主な参考文献
- Ichikawa, H. (2007). 軍人による市民的不服従―選択的兵役拒否と脱走. 広島平和科学, 29, 47–70.
- Ito, K. (2020). 徴兵制を巡る韓国国民の認識変化と『国防改革2.0』の行方. 国際情報ネットワークIINA.
- Miki, Y. (2024). 世界の徴兵制. Global News View.
- Marzia, A. (2022). How counter-recruiters take on the U.S. military. YES! Magazine.
- Amnesty International. (2023). Israel: Conscientious objector Yuval Dag sentenced to prison.